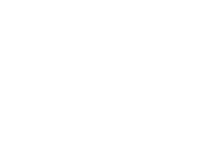2020年に開催された第4回価値デザインコンテストで、経済産業大臣賞を受賞された株式会社バーベキューアンドコー 代表取締役 成田收彌さんにお話を伺いました!

株式会社バーベキューアンドコー
兵庫県明石市松の内二丁目二番地
代表取締役 成田收彌
https://bbqandco.jp/
2023年4月現在、4つのバーベキュー場と1つの店舗を運営。
■明石海峡大橋を一望できる
大蔵海岸BBQ「ZAZAZA」 https://bbqandco.jp/location/zazaza/
■美しく整備された庭の中で楽しむ
大阪市舞洲「森とリルのBBQフィールド」 https://bbqandco.jp/location/forest-rill-bbq/
■自然豊かな公園に彩りを添えるテイクアウトショップ
明石公園「TTT」https://bbqandco.jp/location/ttt/
■神戸の丘に広がる
「KOBE WEST」https://bbqandco.jp/location/kobe-west/
■広い庭で団らんするようにBBQを楽しむ
大阪府堺市「matoi」 https://bbqandco.jp/location/matoi/
事業内容について教えてください
「BBQからひろがるコミュニケーションで、人を笑顔に、地域を明るく。」
という理念で、バーベキュー場の運営をしています。
ただ単にBBQを楽しむ場所をつくっているのではなく、BBQと何か付加価値となるものを組み合わせることで、そこでしか得られない体験を提供しています。
大蔵海岸ZAZAZAについて教えてください
2018年度に明石青年会議所で委員長を受けるにあたって、委員会基本方針に「新しい価値」という言葉を使ったんです。すると、「何を持って新しいとするのか」という質問をいただいて。
とっさに、「『新』という漢字は、『立』っている『木』に『斤』と書きます。0から1を生むことが新しいのではなく、すでにあるものを加工し、バージョンアップさせることを、『新しい』と考えています」と答弁したんです。
とっさの回答にしては、うまいこと言ったなと。(笑)
その着想から大蔵海岸のZAZAZAというバーベキュー場も、「新しい価値」を生むことができた場所です。
すでにある景観に新しさを加えようと思ったら、視点を変えないといけない。
では、高さを10メートル加えたらどうなるだろう?という発想から生まれています。
大蔵海岸は、実は、2001年に歩道橋の事故があった海岸です。
遺族感情はもちろん大切ですし、明石市にとっても当然アンタッチャブルな場所だった。
だからこそ、2019年の4月にZAZAZAをオープンさせるときに、明石市長をはじめ多くの方を招いて、テープカットをしました。そのときに、市長が「ここから素麵流しのようにしよう」言っていたんです。その時は何のことか分かりませんでしたが、後から『第41回全国豊かな海づくり大会』のことだと分かりました。
(https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/dayori2211/pickup6.html)

オープン以降、多くのお客様にお越しいただいていることはもちろん、天皇、皇后両陛下が稚魚の放流をしにこられたりと、想像をしていなかったような形で、場所としての価値を高めていくことができました。「地元の人たちにとっての誇らしい場所」を作り出すことができたと言えるかもしれない、と考えています。
今でこそ舞洲は盛り上がっていますが、大阪市舞洲は、オリンピック誘致ができず、閑散としていた場所。なぜ舞洲にバーベキュー場を作ったのですか?
ここは2014年に開業していますが、入札があったのは2013年、橋下市長の時代で、大阪市の中の不採算事業は見直しなさいと通達があった頃。
当時の『ロッジ舞洲』は雑木林が広がっている荒れた緑地で、約20年間指定管理者制度で野外活動センターを運営しており、一度も宿泊施設として50%の稼働率を超えたことがなく、毎年その赤字の補填として約2,000万円の市税が投入されていたそうです。
入札への参加に踏み切ったのは、「市街地から少ししか移動していないのに、すごく遠くに来た気になる」、この特徴を使えばなんとかなるのではないか?と考えたからです。

そして見事勝ち取ったところ、あれよあれよと、大阪エヴェッサが舞洲を本拠地に、オリックスも大阪に2軍の合宿所を移動させることに。もともとセレッソが練習場を持っていたので、プロスポーツ3球団が舞洲に集結したんですね。
そんなこんなで盛り上がっていたら、2018年11月には『大阪・関西万博』の開催が決まった。
オリンピックの誘致に失敗し、誰も寄り付かなかった場所に入って、わいわい騒いでいたら勝手にいろいろ集まってきた、という感じです。
まさにこの、「何もなかったところに賑わいをつくる」「地域に誇りを創る」というのが我々の事業そのものだと考えています。
バーベキューアンドコーは、ホテル事業から分社化する形で生まれたそうですね。
祖父が前身となるホテル業の創業者で、そこから数えると私は3代目にあたります。
私たちが明石にホテルを作ったころ、明石にはホテルが一軒もなかったんです。明石に出張に来るビジネスマンが宿泊する場所がないという声を聞き、必要だろうということでホテルを建てた。
ですので創業当時から、マーケットがあるからシェアを作ろうというビジネスではなく、「地域の困りごとを解決し、なにもないところに賑わいを作っていく」というスタイルで、世代を超えても、それは変わっていません。
バーベキューも象徴的だと思っています。私達は「スペースをプレイスにする」と言っているのですが、なにもない「スペース」を、どうやったら人の思い出が沁みついていくような「プレイス」にできるのか?と考えながら事業を構築しています。
私の場合は、「みんなやりたくないって言ってる」って聞くと、「やったろかな」という気持ちも湧いてきちゃうという癖もありますね。(笑)
新事業を始めるときの判断基準はなんですか?
地域の困りごとを解決するのが創業当初から変わっていないスタイルだというお話をしましたが、損得勘定は、ビジネスをやる以上、ないとやっていけないと思っています。
だから、まずはとことん合理的に考えます。でも、計算だけを頼りに事業を構築すると、「私じゃなくてもできたかも」という状態になって、自分が生きた意味がないような気になりますし、結局同じ発想のビジネスが多く生まれることでレッドオーシャンになってしまうんです。
それを回避するためには、損得以外の判断基準が必要になります。
損得はもちろん考えるけど、最後の最後は、自分の中にある価値基準でちょっとずらす。
「これをやれば儲かるのは分かってるけど、親からこう言われてるからそっちには行けない」とか「昔からの仲間と約束してるから」とかそういう自分らしさに基づく判断基準ですね。
自分の中に、どんな「掟」が眠っているのか?
それを紐解いて、最後の判断に使っていくことが大切だと思っています。
成田さんが今感じている「社会課題」はなんですか?
私達の事業領域に関する社会課題には、「地域らしさが失われていること」が挙げられると思います。
私は、その課題を解消するためには、まず歴史に向き合う必要があると考えています。(※参考まで https://note.com/coten_inc/n/n3467d0a09f07)
日本の近代化は明治維新後。その頃の日本の大命題は、西洋人から、「日本人もちゃんと民主化できそう。資本主義経済に組み入れられそうだ」と思わせること。
だから、日本は西洋化を一気に進めたんですね。
スピードが必要だったので、全国一元的に整備したことで地方のどこに行っても同じようなものがあるようになった結果、地域らしさが縮小していったし、新しく生まれた概念も、不完全なまま常識化していった。
たとえば、西洋化する前、日本には、自分自身の延長としての「世間」という概念しかなかったのに、「パブリック」と「プライベート」という概念がうまれたわけです。しかし、西洋にはパブリックとプライベートの間の、「パブリックコモン」という概念がある。ちゃんと、「ソト」と「ウチ」の間にグラデーションがあるんですね。
でも日本にはそこがなく、ぱち!っと二極化しています。
そんな状況で、バーベキューは、パブリックとプライベートの中間に、日常の景色をおびき出す装置になると考えています。
バーベキューをアウトドアと言いますが、バーベキュー用品がキャンプ用品の横で売られているのは、実は日本だけなんです。海外ではキッチン用品のところにあります。「今日は気持ちがいいから外で食事しようか」。これが、本来のバーベキュー。
日本の場合は、パブリックとプライベートの概念がばちっと分かれすぎているが故に、家の外に出すということ自体が、ぴんと来ていないんですね。
だから、その中間を充実させることをしたいんです。その結果、その地域らしい人の営みが、旅行者にも視認できるようになる。プライベートな姿は家の中に閉じ込めている現状だと、街にその地域らしさが出てこないんですよね、外に出すのは行儀良い姿だけだから。旅行者が、地域らしさにアクセスできないわけです。これは日本が今後どのように観光業を発展させるべきなのかとも関係します。

公園に、つまりパブリックな空間に、プライベート=日常がはみ出していい。そうすると、「公園に行くと日本人の素のところが見える」と認知されるようになり、そこが観光地化する。さらにそこで食べられているものが地域らしいものだと、さらに地域らしさが出てきますよね。
このまま行くと、地域らしさがどんどん失われていきます。
プライベートから少しはみ出して、場所、プレイスを作っていくことで、そこがまた地域の誇りとなっていくのではないでしょうか。
何もない「スペース」を、賑わい、地域の人たちの誇りにもなる「プレイス」にしていくために、大切なことはなんでしょうか。
例えば、私は庭を「自然と作為の融合」と定義しています。
自然は美しいと言われますが、たとえばジャングルって「美しく」ない。怖いですよね、ジャングル。
イングリッシュガーデンは「美しい」けど、ちっとも自然の姿じゃない。
要は、人間の手がかかっているから美しさが生まれるんだと思うんです。
たとえば大蔵海岸の目の前には、瀬戸内海と淡路島が自然のものとして存在します。そこには明石海峡大橋のように、その場所の独自資源として奪えない地理的なもの(自然)に対して人の作為が施されています。人はそれを美しい風景と言ったりします。「美」とは理屈で説明できない正しさのことです。
地理的な独自資源はどの地域にもあるはずです。それに対して、「この角度から座って眺めたら絶対にきれい!」「こんな建物をこんな意図で配置したらかっこいい!」と思えるものを作為的にデザインし、パブリックにプライベートが溢れている空間として機能させることができれば、それは奪いようのない地域の価値になるし、新しい価値を生み出すことになり、地域の人たちにとって誇れる「プレイス」になると思います。そういう場所は絶対にそれぞれの地域にあります。
それが、僕らバーベキューアンドコーの領域の社会課題の解決となると思っています。
アフターコロナのインバウンドについてのお考えをお聞かせください。
大蔵海岸ZAZAZAには、外国の方も時々来られます。でも、明石はナイトシーンが少ないこともあり、日帰りばっかりなんです。神戸も大阪も姫路も近いですしね。
次のポイントはまさしくそこで、自治体ベースでインバウンドに対する指針をちゃんと持って、旅行代理店とも協同していくというような、エリアマネジメント要素が重要になってきます。立場が違うもの同士、このエリアをどうやって盛り上げていくか、どうやって協同していけるか、という視点がポイントになります。
もちろん立場が違えば価値観は異なりますが、そんな時こそバーベキューが活躍します。価値観はそもそも異なっていていいんです。むしろ価値観が完全に一致するというのは怖いことですよ。それは全体主義ですもんね。
大切なことは、「価値観が揃わないということを受け入れる」ということに対して「合意している」こと。
価値観は違っているけど、「同じ釜の飯を食った仲間だろ?」つまり「同じ地域を盛り上げようとしてる仲間だろ?」という合意を通じて、エリアマネジメントパートナーになっていかないといけない。
我々はデコとボコであり、パズルみたいな形でお互いの得意不得意を埋めていければ良い連携が生まれ、その結果、企業がもっと地域から愛されるような形になるのではないかと思います。
仲間を作っていくためのポイントが、「価値観が異なることへの合意」以外にもあれば教えてください。
知らない人同士が、知り合いになり、そして仲間になっていく過程には、「戦略の共有」が必須だと考えています。
たとえば部活。たとえば青年会議所活動。同じ戦略を共有することで仲良くなっていく、という経験をしたことがある人は多いでしょう。
戦略の共有を言い換えると、「同じ世界に入ること」です。

たとえば、一緒に海外旅行に行った。これも、同じ世界に入ったことになります。
海外旅行に行く前の自宅と、海外旅行から帰ってきたときの自宅、ちょっと違って見えますよね。
別の視点を手に入れて、別の視点を手に入れたもの同士が地元に帰ってきたときに、
「前まで気にならんかったけどさ。あの視点から言うと、こうだよね」みたいな、二人だけの秘め事みたいなのができると、一気に仲間化する。
そんなふうに、「世界に没入する」「一緒の世界に入る」というキーワードで探していくと、いろいろ見つかります。
バーベキューも、同じ世界に没入することができるコンテンツだと思います。仲間作りのためのおすすめの方法はありますか?
まず、肉の焼き方ですね。
私は焼き肉が好きですが、あえて言います。焼き肉スタイルでお肉を焼いていると、同じ世界に入りにくいんですよ。なぜなら、焼き肉で起こることは「陣地争い」だからです。「この網の上で、この肉は俺が育てている。絶対に取らさない!」みたいな、お互いこういう状態になる。これは分断ベクトルですね。
BBQをするなら、ぜひ、塊肉を焼いてください。
陣地争いの分断軸から、「同じ肉を分け合った俺たち」という、シェア軸に変わる。
焼き終わったら、ステーキみたいに切り分けていくのではなく、まずは真ん中でズバっと切って、肉の断面をみんなに見せてあげてください。うまく焼くスキルがあれば「この焼き加減は絶対うまいヤツ!」という反応がありますから、みんなで同じこの体験を共有してみてください。これで同じ世界に入れます。
「あのときのお肉うまく焼けてたよね」と、あとからもその世界を共有できます。
焚き火も同じ世界を共有できるコンテンツですね。普通に対話すると向き合う形になりますが、焚き火があれば、きっとみんな焚き火を見ながらしゃべる。同じサイドに立つわけです。だから空間デザイン的に、対立構造を消していくと、自然と仲間化していくんです。そういう工夫は、バーベキュー場にどんどんしていくべきですね。

バーベキューが上手な人の特徴はありますか?
バーベキューが上手な人はチームビルディングが上手と言われているんです。
和を作る、仲間に引き込むのが上手なんですね。
バーベキューをみんなでやっていると、端っこで静かにしている人もいますよね。でもその人は静かにしているのが好きなんじゃなくて、関わり方がわからないだけだったりします。
そういう人には水鉄砲を渡してあげるんです。そして、「火が上がったらそれで消して!」と役割を与える。自分も一員として担いを担ったと思うと輪の中に入れます。
お腹が減っている状態だから、みんなのモチベーションがある中で役割をうまく振っていくことは、バーベキューが上手な人の力です。
バーベキューは、コミュニケーションツールとして本当に有用です。
ただ、日本の悪いところは、「下っ端が焼く」という風潮。そうではなくて、チームビルディングのために、逆に一番偉い人が焼くべきなんです。誰と誰が仲良いか、とか、すぐわかる。
日本人はこれが身につくだけで、コミュニケーションがすごくバージョンアップすると思います。
日本の教育現場では、意見が対立したときのコミュニケーション教育が十分になされていません。「自分」の感覚が同心円状に広がっていった先に「世間」も広がっているという世界観で生きていたので、意見が違うと村八分、という常識の中で生きている。
でも本当は意見対立してからがスタートで、そこからどうして行くか、の方が建設的で、そのような振る舞いを学ぶべき。
バーベキューを通じてそんな教育もできます。
今後の事業展開を教えてください。
デベロッパーからどんどんバーベキュー場を作りたいという声がかかっている状況で、同時進行でたくさん企画が進行しています。
ただ、それらを全部自社でやるのが良いのかどうか、検討しているところです。
たとえばこの事業は青年会議所との親和性が高いと思っていて、どういうネットワークを持ってそれを運営し続けて行くのかとか、どういう地域らしさをインストールしていくのかということを考えると、JCと連携するのもいいのかな、という気持ちもあります。
それから、日本人のコミュニケーション能力が、公園開発がきっかけになってどんどん底上げされ、地域が活性化していく、みたいなことがビジョンとして描けると思っています。
日本の公園の問題も歴史の問題を孕んでいるんです。
日本の公園は社会福祉として経済発展が進んだ時代に整備されてきました。
しかし、人口や税収の減少を想定した仕組みになっておらず、予算がつけられなければ老朽化の問題に対応できない状況にあります。そこで、民間活力を公園にも導入できるように法改正されましたが、まだまだ機能していないところも多い。
では維持管理や更新の予算が縮小された公園に何が起こるか?
ゴミ回収の頻度や草刈りの頻度が下がり、荒れていき、不良の溜まり場になります。街の観光価値も下がりますし、健康増進のための場も奪われます。すると、住みたい・働きたい・遊びに行きたい場所ではなくなってしまい、周辺不動産の価格が下がる。
いい公園はというと、きれいで、週末にはイベントが開催されていて賑わいがあり、照明もきちんと整備されているので夜も明るく、ジョギングできる。そうすると近隣の不動産価格は上がります。ハードとしての不動産が全く同じ、建築コストが同じでも、周辺の環境を良くすることで価値を高めることができます。
この事業のスピードを上げる方法の一つは、所有と運営の分離だと思っています。同時多発的にやっていこうとすると、イニシャルコストに耐えきれないからです。オペレーターである私たちが、地域を良くしたいと考えているホルダーとパートナーシップを組む。地域のホルダーは同時にその施設や街のアンバサダーでもある、みたいな関係を構築できるかもしれません。このように所有と運営を上手に別けられれば、事業展開のスピードは上がると思います。
価値デザインコンテストに出てよかったことはありますか?
まず一つは、信用がついたことです。
自分の事業には社会的に大きな意味があるということを、どれだけ上手にプレゼンしたとしても、実績には敵わないんですよね。
評価された、という信用を得ることはもちろんですし、後になってからも事業のブレなさを証明してくれるものだと思います。
人を納得させるためには3つの態度があるといわれています。
1つは、論理的であること。2つは、情熱的であること。そして3つめは、倫理的であること。
人の心を最も打つのが「倫理的な態度」であると思っているんですが、そのためには一貫性があることが必要です。
過去の受賞歴は自分の一貫性を強化してくれます。
もう一つは、アウトプットできる機会になったことです。
インプットとアウトプットでは、インプットが先だと思っている人が多いですが、私はアウトプットが先だと思っています。
プレゼンテーションというアウトプットがあるからインプットできるようになる。
自身をアイデア枯渇状態にした方が、世界が自分に語りかけてくれるようになります。
どういうことかというと、たとえばあるお題に100個アイデアを出すとする。50個超えるとアイデアが出なくなってくる。そこからどれだけ振り絞っても、80個くらいで限界がくる。その状態で図書館に行ってみると、全ての本が「俺やで」「俺にヒントあるで」って語りかけてくるんですね。
アウトプットが絶対に先です。一度カラっカラにしてみると、ありとあらゆることが学びになります。そうしてやっと、スタートに立つ。
まずは絞り出すことです。
ですが、一人で何の評価者も締め切りもなく、アイデアを絞り出すのはなかなか難しいことです。
こういうコンテストなどの機会を使ってみると、きっと違う世界が生まれると思います。
最後に成田さんの「夢」を教えてください

日本中のパブリックスペースに人々のプライベートがはみ出している状態を作り出すということをしたいです。「生きているだけで幸せな日本」を作りたい。
ちょっと移動するだけでハッピーな気持ちになれるような楽しい国って、すごく幸せだと思うんです。地域らしさに加えて、地域に根ざしているもの、文化が街に溢れている状態を、バーベキューを通じて作って行けたらと思います。
(取材:社会課題解決推進委員会 副委員長 川上智之、委員 関谷昌子)