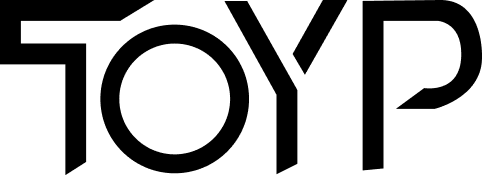| 氏名 | 品川 優 |
| 所属企業・団体名 | 株式会社An-Nahal |
| 所属企業・団体役職 | 代表取締役 |
| 推薦青年会議所 | 一般社団法人横浜青年会議所 |
| 活動カテゴリー | ビジネス、経済、起業, 青少年育成、世界平和、人権 |
| SNS・HP | https://an-nahal.com/ https://note.com/yulatifa https://www.linkedin.com/in/yu-shinagawa/ https://x.com/yu_annahal |
活動エリア及び活動内容
2019年に株式会社An-Nahalを創業し、以来、国籍や文化、言語、性別、障害の有無など、あらゆる違いを力に変える社会の実現を目指して活動してきました。主に企業・大学・自治体に対して、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を推進するための教育プログラムや組織開発支援を提供しており、これまでに40か国以上・8000人超を対象とした異文化研修やキャリア支援を行ってきました。
また、外国人起業家の支援や、地域に根ざしたイノベーションコミュニティの運営など、多文化共生社会の実現に向けてセクターを超えた連携に取り組んでいます。地元横浜の国際化推進に関わる取り組みや、企業と留学生をつなぐ異文化メンタリングのプログラムの運営、そしてプログラムを通じた研究活動にも取り組んでいます。
活動内容写真




経歴 自己PR
「多様な人材が協働する社会」を目指し、2019年に株式会社An-Nahal(アンナハル)を立ち上げました。高校生の時に日本にクラス難民の方と出会い、多様な文化や背景を持つ人々が日本社会のなかで孤立し、力を発揮しきれない現実を目の当たりにしてきました。
そのたびに、「日本を多様性を受け入れる社会に変えたい」という思いが強くなりました。何より私自身が同調圧力のプレッシャーを感じる中、世界中の仲間から「人と違っていい」と教わり勇気をもらってきました。一人ひとりが安心して自分らしく働ける組織や地域社会をつくりたい――。その想いから、国内ではNPOでの難民就労支援、国際的には世界銀行でのプロジェクト運営や、コンサルティング会社での経験を重ねてきました。
そして2019年、社会と組織の“橋渡し”を担う存在として、An-Nahalを創業しました。社名のAn-Nahal(アンナハル)は、日本語の「春」と、アラビア語で「ミツバチ」を意味する“An-Nahl”を掛け合わせた造語です。厳しい冬を越えて、春を迎えるように――誰かにとっての「春」が訪れるきっかけをつくりたい。そして、ミツバチのように人と人、組織と人、社会と多様な才能をつなぎ、新しい可能性を咲かせていきたい。そんな想いを込めています。
現在は、企業のダイバーシティ&インクルージョン研修、外国人留学生との相互メンタリングプログラムなど、多方面で「違いを力に変える仕組みづくり」に取り組んでいます。
これまでの実績等
2019年:ボストンの女性社会起業家育成プログラムJWLIフェローに選出/世界経済フォーラムGlobal Shapers任命
2020年:NEC推薦枠で「社会起業塾」プログラムに参加
2021年:日本財団の若手社会起業家支援プログラム「Social Change Makers」第5期生/神奈川県スタートアップ支援プログラム採択
2022年:トヨタ財団「外国人材受け入れと日本社会」研究助成に採択
2024年:HRアワード入賞、日本HRチャレンジ大賞奨励賞/世界中の女性リーダーを支援するVital Voices Global Fellowshipに日本人として3人目に選出
VISION(この活動を通してどのような未来を実現したいか)
私は、「多様な人材が協働する社会」を実現したいと考えています。
その原点は、高校時代に出会った難民の女性との交流です。戦火を逃れ、日本にたどり着いた彼女が、社会の無理解や偏見のなかで苦しんできた話を聞いたとき、「日本社会を変えたい」と強く思いました。その後、内閣府の青年国際交流事業「世界青年の船」への参加を通して、13か国から集まった仲間と出会い、「違いがあるからこそ、お互いの強みを活かすコラボレーションが生まれる」ことの可能性やワクワクを体感しました。
現在の日本は、世界的に見ても多様性に対する意識が低いと言われています。ランスタッドの調査では異文化環境で働く意欲は日本が最下位、IMDの国際競争力ランキングでも管理職の国際経験も先進国中最下位となっています。
そのような社会では、知らないことへの恐れが分断を生みます。
だからこそ私は、教育と対話を通じて、違いが「協働の源」になることを伝えたい。異なる背景をもつ人々が、互いに学び合い、支え合いながら新たな価値を生み出す社会。それが、私が目指す未来です。
ACTION(ビジョンを実現するために今行っている具体的な活動)
現在多様性の価値に触れられるような原体験を創出するプログラムを開発・提供しています。特に注力しているのが「相互メンタリング」という独自の手法です。これは、外国人留学生と日本のビジネスパーソンが互いに学び合い成長を支援するプログラムであり、トヨタ財団の助成を受けて2年間にわたり実施しました。今は100名を超えるアラムナイコミュニティができています。
このアプローチは、パスポート保有率18%という異文化と触れる機会の少ない日本人に対し異文化と関わる原体験となり、留学生にとっては日本社会との接点や働く上での文化を理解する場となっています。
また、地域とも連携し、外国人起業家への支援体制整備や、地域経済とグローバル人材を結びつける新たな仕組みづくりも進めています。
IMPACT(あなたの行っている活動は社会にどのような影響を与えているか)
私たちの活動を通じて、目に見える変化が起きています。
例えば、相互メンタリングプログラムでは、参加したビジネスパーソンが異文化への理解を深め、海外プロジェクトに立候補したり、留学生の目線から見た自社の採用広告や施策の見直しを行った方もいます。
また、参加した外国人留学生の就職率は全国平均の約2倍(平均が35%のところ、プログラム卒業生は68%)に達し、日本語学習の意欲向上など、双方にとって有益な変化が生まれています。
このプログラムは厚生労働省後援の日本HRチャレンジ大賞奨励賞やHRアワードにも入賞し、注目されはじめています。
多様性の価値を伝える上で最も難しいことは「イメージが沸かない」こと。
だからこそ、私たちは大学・企業・行政など多様な人・組織と連携し、「多様性の価値を可視化する場作り」をこれからも一貫して取り組んでいきます。
VISION(この活動を通してどのような未来を実現したいか)
"私は、「多様な人材が協働し、新しい価値を創造する社会」を実現したいと考えています。
その原点は、高校時代に出会った難民の女性との交流です。戦火を逃れ、日本にたどり着いた彼女が、社会の無理解や偏見のなかで苦しんできた話を聞いたとき、「日本社会を変えたい」と強く思いました。その後、内閣府の青年国際交流事業「世界青年の船」への参加を通して、13か国から集まった仲間と出会い、「違いを恐れず、違いを力に変える」ことの可能性を体感しました。
現在の日本は、世界的に見ても多様性に対する意識が低いと言われています。日本人の異文化環境で働く意欲は最下位、管理職の国際経験も先進国中最下位。そのような社会では、知らないことへの恐れが分断を生みます。
だからこそ私は、教育と対話を通じて、違いが「協働の源」になることを伝えたい。異なる背景をもつ人々が、互いに学び合い、支え合いながら新たな価値を生み出す社会。それが、私が目指す未来です。"
ACTION(ビジョンを実現するために今行っている具体的な活動)
"そのビジョンを形にするため、私は異文化間の相互理解を促進する教育プログラムを多数開発・提供しています。特に注力しているのが「相互メンタリング」という独自の手法です。これは、外国人留学生と日本のビジネスパーソンが互いに学び合うプログラムであり、トヨタ財団の助成を受けて2年間にわたり実施。このアプローチは、日本人にとっては異文化と関わる原体験となり、外国人にとっては社会との接点となる「協働の場」を創出しています。
また、地方自治体や商工会議所とも連携し、外国人起業家への支援体制整備や、地域経済とグローバル人材を結びつける新たな仕組みづくりも進めています。地域の課題を世界とつなぎ、持続可能な成長につなげることが、私たちの役割だと考えています。"
IMPACT(あなたの行っている活動は社会にどのような影響を与えているか)
"私たちの活動を通じて、目に見える変化が起きています。例えば、相互メンタリングプログラムでは、参加したビジネスパーソンが異文化への理解を深め、新しいプロジェクトに挑戦する意欲を持つようになりました。また、参加した外国人留学生の就職率は全国平均の約2倍に達し、日本語能力も飛躍的に向上するなど、双方にとって有益な変化が生まれています。
さらに、私たちのプログラムは厚生労働省後援の日本HRチャレンジ大賞でも評価され、全国に展開できるモデルとして注目されています。国際女性デーの取り組みでは、行政・大学・在日外国大使館・海外商工会議所と連携し、多様性の価値を広めるイベントを開催。地方から世界へと広がるインクルーシブな社会づくりを、着実に進めています。"