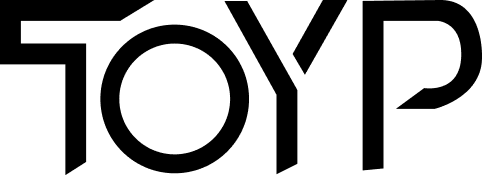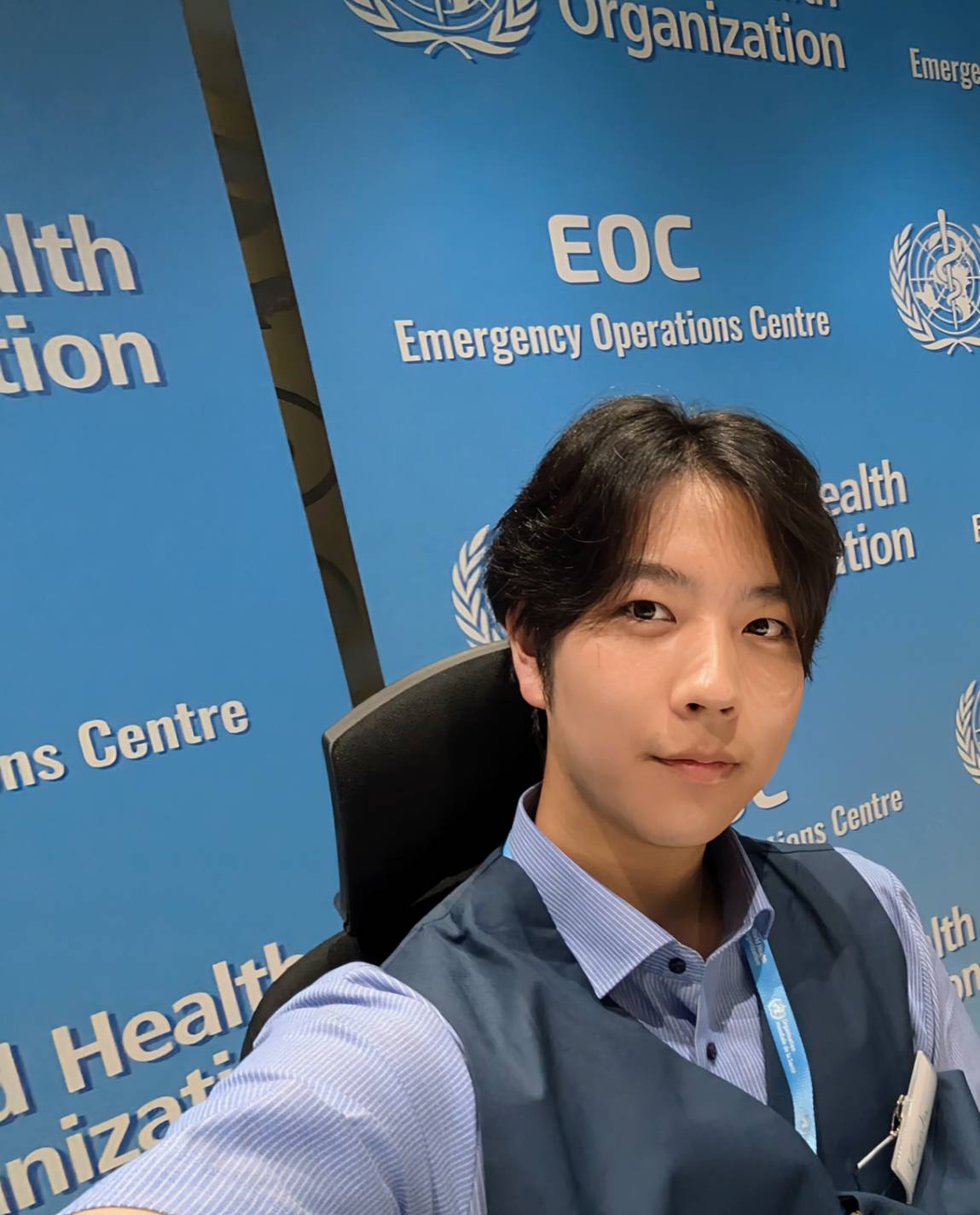
| 氏名 | 井上 幹太 |
| 所属企業・団体名 | 団体名: 日本文化アートテックブランド「JAPAN MODEL NⅢ」 |
| 所属企業・団体役職 | 代表 |
| 推薦青年会議所 | |
| 活動カテゴリー | ビジネス、経済、起業, 学術, 文化, 科学技術 |
| SNS・HP | Wantedly(詳細情報): https://www.wantedly.com/id/kanta_inoue_ZenU BaseMe(キャリア画像付き): https://baseme.app/users/kanta_aiengineer?tab=photos Instagram(自己プロジェクト発信): https://www.instagram.com/kanta_biz10110/ JAPAN MODEL NⅢ公式ブランドページ: https://v0-niii.vercel.app/ JAPAN MODEL NⅢブランド公式資料: https://drive.google.com/file/d/19bBMXKrhYXi5ox4d1yRR50CwgvBnvMzj/view?usp=sharing |
活動エリア及び活動内容
私の金融教育への関心は高校1年次(2022年)に始まり、当初は所属するN/S高等学校と村上財団が手掛ける「N/S高投資部」での株式投資への挑戦から始まった。2022年のMIRAI金融教育プログラムと題して学生団体FIN/School. の正式発足まで段階的に発展を遂げることができた。このプロセスでは、延べ50名以上の金融の専門家(FP/アナリスト)や中学校教員、大学教授、事業家へのインタビューを実施し、日本の金融教育の課題と解決策を体系的に調査・分析を実行した。
私の活動は2022年から現在に至るまで、国内外でのMIRAI金融教育プログラムを中心とした金融教育改革プロジェクト活動がほとんどだ。国内は東京都および京都府を拠点とし、海外はフィンランド(Aalto University Executive Educationプログラムへの参画)やアメリカ、スイス-ジュネーブなどの先進地域における現地の金融教育モデルや起業家マインドを学び、その知見を日本に還元する活動を展開した。
累計関係者は、1,000名(2024年2月時点)を超え、その内訳は高校生10%、大学生20%、社会人70%となっている。高等学校や大学の学生団体として定期的な金融教育イベントやワークショップを実施。
例として、UT-LAB(東大本郷)公認アンバサダーとして企業連携やインターン活動に参加し、最新の金融知識を実践に活かすとともに、他校の学生へ実践的な学びの機会を提供している。
さらに、フィンランドのJ-StarXプログラムやペンシルベニア大学ウォートン校主催の高校生国際投資コンペティションなど、国際イベントへの参加を通じて、単なる理論ではなく実際の市場環境を体感しながら金融リテラシーの向上を図っている。プログラム修了6か月後の追跡調査では、参加者の42%が実際に少額からの資産運用を開始し、その93%が長期的な資産形成の視点で継続しているという結果もあり、金融教育の重要性を体感した活動となった。
現在は、地元である京都の伝統文化の維持が人口減少で苦慮を強いられている現状を知り、日本文化をこれからもより多くの人に親しんでもらう方法を模索する中、金融に触れた経験・京都文化で育った幼い時の経験をもとに「NFTアート」に着目。NFTアートを通じて、地元の人口が減る中で、世界の日本文化を愛する人たちの「応援」を日本文化NFTアートを保有することでコミュニティを築き、文化の保存につながると考え、日本発学生生まれの日本文化をテーマにしたNFTアートブランド「JAPAN MODEL NⅢ」を設立。地元の文化を世界で盛り上げるため活動を続ける。
活動内容写真


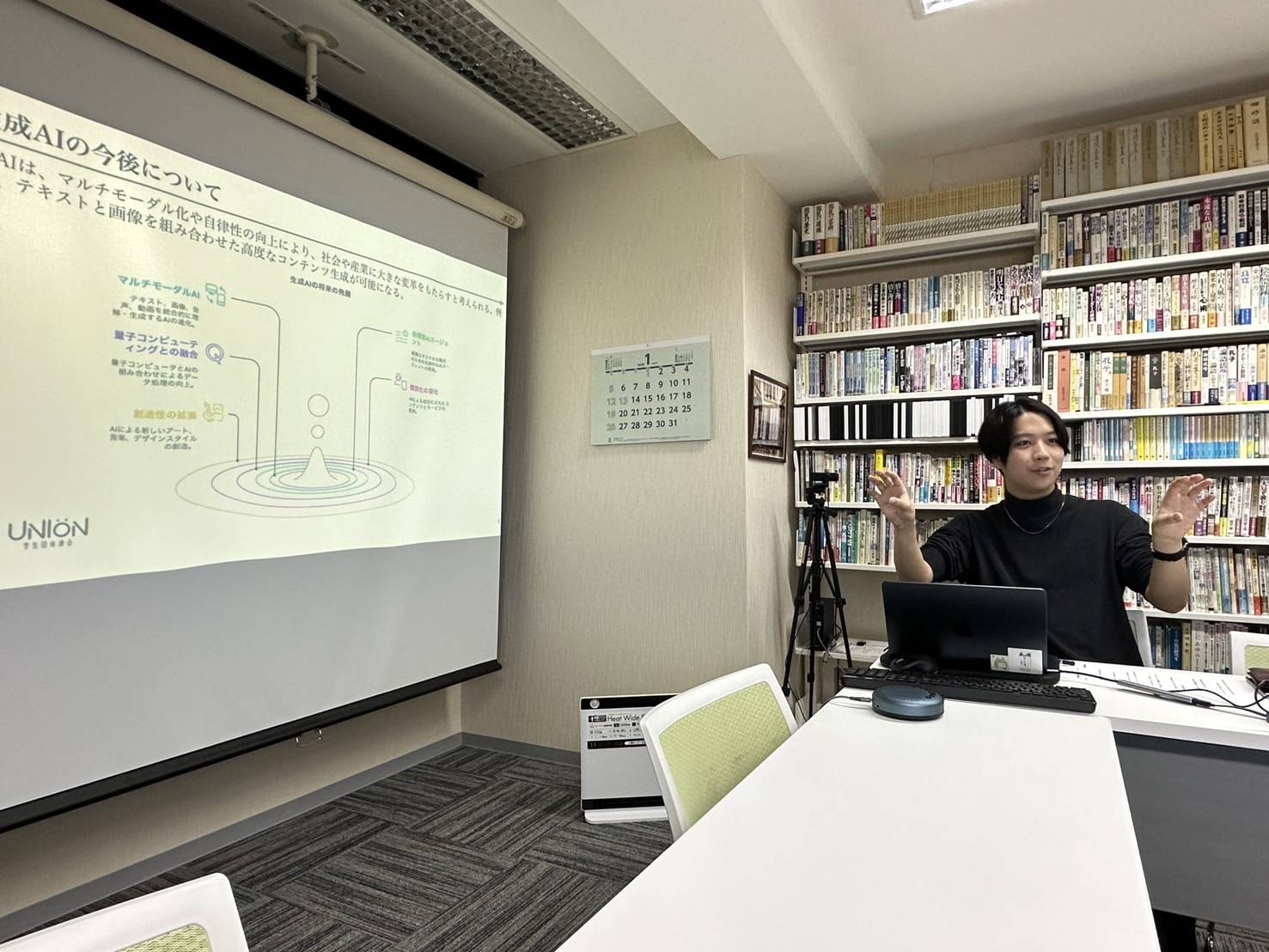

経歴 自己PR
「人は境遇を選べないが、選択を重ねて未来を創れる」—小学生時代の不登校から一歩ずつ前進し、中学生Webライター、高校生金融研究者へと成長。国際経済学オリンピック入賞、世界的教育機関での学びを経験する中で、経済教育の重要性と、誰もが自分らしく夢を追える社会の実現への使命感を強く抱くようになりました。「与えられたるものを受けよ、与えられたるものを活かせ」を体現し、困難を乗り越えて前進する日々を送っています。
不登校経験と成長
小学校時代、コミュニケーションが苦手で友達との会話が全くない学校生活を送っていました。先生からは「友達と仲良くしなさい」と言われましたが、仲良くしたい気持ちはあるものの、その方法がわかりませんでした。プレッシャーの中で、コミュニケーションをしたいができないという葛藤に日々苦悩し、不思議もなく不登校になりました。友達の親からは「不登校」というレッテルを通じて「不出来な子供」というフィルタを通して見られ、無言のプレッシャーと見下されているように感じる日々から抜け出さなければならないという思いを抱えていました。
中学校に進学後、ある日の家庭訪問で学校の先生から転職したいという想い(学校の先生の労働環境の悪さから)を聞き、稼ぐことの難しさ、社会を生き抜くための経済力に関する大人の思いを感じました。その時、私は「大人になりたい」と強く感じました。「不登校は不良だ」「不登校は出来損ない」「不登校になったら将来生きていけない」というレッテルを変えたい、そして誰よりも早く大人になって将来見返してやりたいと思った私は、読書が好きだった頃を思い出し、中学2年生の時にWebライターの仕事を始めました。
しかし、そこからは失敗の繰り返しでした。ブログは結果が出るまでに膨大な時間と文章が必要であり、単なる文章では意味がなく、誰もが見て役に立つ文章が必要だということを学びました。ライターデビュー3ヶ月目、売上は1ヶ月にわずか13円でした。これでは大人どころか、勉強もせず1日中パソコンと向き合う不良になってしまうと危機感を覚えました。
そこで私は、企業や個人ライターに直接私の書いた文章を見てもらい、トライアンドエラーを繰り返しました。添削を10回行い提出し、夜23時から2000文字の添削依頼が送られてくるような生活を送りました。そして中学2年生が終わる頃、お茶を販売する企業から直接文章の執筆依頼をいただき、そこからは早い展開となりました。文章を書いて半年、本を読み、プロに文章を添削された私の文章は大人のライターと比べても遜色なく、ユーザーに役立つ記事となりました。
このような逆境からの成長を経験したことが、「逆境からの成長」という私の信念の礎となっています。
学業および部活動での実績
通信制高等学校入学後、投資部、政治部、研究部に所属し、経済学の基礎と市場の仕組みを徹底的に学びました。研究部では金融市場の変動予測研究に注力し、実践的な分析手法を習得しました。この成果が国際経済学オリンピック日本代表選考全国大会でのケース部門3位獲得(2023年4月)につながりました。
最新の技術活用能力
生成AI技術を駆使した業務効率化の実績(2025年1月)として、1日100人規模のスカウティングとフィルタリングを実現しました。この技術力を金融教育プログラムやNFTプロジェクトに応用し、革新的な教育・文化プロジェクトを展開しています。
国際的な経験の蓄積
海外派遣プログラム(フィンランドのJ-StarX、ペンシルベニア大学ウォートン校主催投資コンペ)や大学研究機関でのインターン活動を通じ、実践的な知識と国際的視野を獲得しました。
公的評価の獲得
松下政経塾スピーチコンテストで優良賞を受賞し、金融教育の重要性を広く訴える実績を上げました。
組織基盤の確立
金融教育プログラムの継続的運営のため、①年間運営予算の確保(協賛企業3社からの支援)、②コアスタッフ7名体制の確立、③月次PDCAサイクルによる改善プロセスの構築、④オンライン教材のデジタルアーカイブ化を完了しています。これにより、リーダー一人に依存しない組織基盤を構築し、5年以上の活動継続を可能にしています。
私はこれらの経験と理念に基づき、金融教育を通じた資産形成の機会拡大と経済的不平等の解消に寄与することを目指し、今後も学生団体運営、国際コンテスト、企業連携を通じて自己成長と社会貢献を両立するリーダーとして活動を継続する決意です。
私の座右の銘である「与えられたるものを受けよ、与えられたるものを活かせ(哲学者エピクテトス)」この言葉は、自分の弱みを受け入れ、自分の強みを活かす姿勢を説いた言葉であり、発達障害、不登校という弱みを持つことを受け入れ、私自身の行動力、好奇心という強みを活かす姿勢の大切さに気付かされた言葉です。これからもこの言葉の教えを心に秘め、私の身近な人を幸せにできる活動を続けたいと考えています。
VISION(この活動を通してどのような未来を実現したいか)
すべての人に幸せを、すべての子どもに夢を追う力を。世界の教室で見た真実—紛争地域でさえ子どもたちは学びを求めています。フィンランドの教育現場、スイス・ジュネーブの国連での経験から確信した使命があります。それは、お金の不安から解放され、誰もが平等に教育を受け、自分の可能性を追求できる世界の実現です。金融知識という鍵で、子どもたちの未来を解き放ちたい。
私が目指す未来は、「誰もが公平に金融知識を身につけ、お金に困らない社会」です。現代日本では金融リテラシーが十分に普及しておらず、統計上、約8割の個人投資家が投資で損失を被っている現状は、資産格差の拡大や経済的不平等という深刻な問題を引き起こしています。そこで2050年までに、若年層の金融リテラシー向上率を80%以上(世界トップ水準)、個人投資家の損失率を50%以下に低減させること(先進国基準)を具体的な目標と位置づけ金融教育の促進に注力したいと考えています。
フィンランドの学校訪問、スイス・ジュネーブの国連機関訪問を通じて、世界の子どもたちの声に直接触れる機会を得ました。そこで痛感したのは、戦争や紛争の中でさえ、子どもたちは懸命に学びを求めているという事実です。戦争で被害を受けた子どもたちが残した声の記録—「爆撃の音の中でも勉強がしたい」というメッセージに、私は深く心を動かされました。「私たちにできることはないのか」という問いと向き合い続けた結果、金融教育という切り口から子どもたちの未来を支える活動に邁進することを決意しました。
また、私自身が小学校から中学校にかけての不登校、ADHD/ASD(発達障害)といった逆境を抱える中で、学校教員の方々からの励ましなど周囲の支援を受け現在のような活動に取り組めるまでに成長できた、その経験は金融教育改革への情熱と行動力の源泉にこれからも残り続けると今改めて痛感するところです。
私のビジョンは、単なる知識の伝達に留まらず、一経験者として実践的な学びの場、困ったときに頼れる環境を提供することで、資産格差の是正と持続的な経済成長に寄与する社会の実現に貢献することです。世界中の子どもたちがお金の不安なく、自分の夢を自分の力で掴めるチャンスを得られる世界—それが私の目指す未来です。最前線に立つ子どもたちのパートナーとして、彼らの可能性を解き放つ活動を続けていきます。
ACTION(ビジョンを実現するために今行っている具体的な活動)
「知識を授けるのではなく、共に創り、共に学ぶ」をモットーに、3つの柱で活動を推進しています。実践型金融教育では、学生が主体となって市場を体験し、ペンシルベニア大学ウォートン校主催の投資コンペなど国際舞台での挑戦も積極的に支援。日本文化とNFTの融合プロジェクト「JAPAN MODEL NⅢ」では、伝統文化の継承と経済的価値創出を両立させる新たな道を切り開いています。子どもたちと共に歩むパートナーとして、彼らの夢を現実にする橋渡し役を担っていきます。
私の具体的な取り組みは、以下の三本柱で展開しています。
(1)金融教育学生団体の活動と教育イベントの開催
高校在学中に、投資部、政治部、研究部などで実践的な金融プロジェクトを多数実施。
学生団体の創業代表として、国内外での金融教育イベントを企画し、多くの学生に体験型の学びを提供。
大学研究機関や企業とのインターンシップを通じ、最新の金融知識と実務経験を蓄積、その成果を他校の学生に展開中。
金融教育プログラムは、①実際の市場データを用いたシミュレーション、②プロの金融アドバイザーによるメンタリング、③グループでの投資戦略構築と成果発表の3段階で構成され、従来の座学中心の金融教育と差別化しています。実際の投資体験を行い、その結果と心理的変化を分析するという独自手法の開発を行っています。
この活動を通じて、金融知識を「教えられるもの」から「自ら獲得するもの」へと変える教育革命を起こし、子どもたちが自分の力で経済的自立への第一歩を踏み出す手助けをしています。
(2)国際コンテストおよびイベントでの実績
国際経済学オリンピック(日本代表選考全国大会)ケース部門:3位獲得(2023年4月)
研究部での金融市場予測活動を通じて培った分析力が評価される
フィンランドへの短期留学経験を活かした国際的視点での提案が高評価
ペンシルベニア大学ウォートン校主催の投資コンペでは、ブラジルのエネルギー市場における環境への影響、先進国のデジタル産業の発展をもとにポートフォリオを構築、無事プログラムを修了。
フィンランドのJ-StarXプログラムでは、選抜された高校生10名(その他大学生枠40名)のうちの一人として、日本の金融教育改革に関するプレゼンテーションを実施し、第1期生として採択される。
松下政経塾スピーチコンテストで優良賞を受賞し、金融教育の重要性と自らの取り組みを高く評価される。
YouTube公式チャンネルを通じた金融教育コンテンツの発信(2022年3月~)
Instagram公式アカウントによる定期的な活動報告と金融知識の普及(2023年1月〜)
これらの国際交流を通じて、「教育に国境はない」という確信を得ました。フィンランドの教育現場、スイス・ジュネーブでの国際機関訪問で見た光景が、私の活動の原動力となっています。世界中の子どもたちが、どんな環境でも学びへの情熱を失わない姿に、私たちが提供すべき教育の在り方を教えられました。
(3)未来実現の計画
2025年2月に設立したJAPAN MODEL NⅢ(エヌスリー)を通じて、日本の伝統文化とNFTを融合したラグジュアリーブランドを展開中です。日本の伝統と未来のイノベーションを融合させた革新的なNFTブランドとして、世界中のコレクターに新しい価値を提供しています。既に初期コレクションの設計が完了し、プレセール段階への移行準備中です。生成AI技術を活用した業務効率化のノウハウを持ち、1日あたり100人規模のスカウティングやフィルタリングを実現しています。この技術・経験を金融教育プログラムにも応用し、パーソナライズされた学習体験を提供する計画です。
既存の金融教育イベントや学生団体活動の実績を基盤に、将来的には東京都教育委員会、京都府教育委員会、大手銀行(2023年11月よりパイロットプログラム共同実施)などとの連携強化を図りたいと考えています。
政策レベルでの金融教育普及に向けて、①全国高等学校PTA連合会との共同提言書の作成(2024年9月完成予定)、②文部科学省「新学習指導要領における金融教育拡充」に関する意見交換会への参加実績(2024年1月、3月)、③地方自治体(京都市、渋谷区)との「若者向け金融教育推進に関する覚書」締結(2024年2月)など、制度的アプローチも並行して進めています。
さらに、【JAPAN MODEL NⅢ(JMN3)プロジェクト】として、日本文化×NFT×GenAIの融合により、伝統文化と金融・AI技術で日本文化の価値を再定義・変革する取り組みを推進しています。
具体的な連携先例:
自治体:東京都(例:渋谷区、新宿区)および京都市(例:下京区、上京区)などを想定
金融機関・企業:大手銀行を想定
文化・関連企業:生成AI技術・共同制作支援、地域連携・コネクション獲得支援、インキュベーションおよびMVP実証機会提供などの連携で地方の人口減少による文化の減少を防ぎ、日本文化の復活を目指しています。
プロジェクト概要:
日本文化継承×NFT×AIアート: 京都文化を始め日本が誇る地域固有の文化を「未来の文化資産」としてNFTアートに昇華。
技術融合: ブロックチェーン技術、生成AIおよび3Dレンダリングを活用し、日本文化の真正性と流通性を担保。
イベント企画: 「ルーブル美術館×日本文化コラボ特集展」などの国内外での展示会・共同企画の実施を目指す。
UTコンテンツ: NFTに連動した特典(施設利用権、共同制作、オーナーシップロイヤリティ等)を付与し、参加者や地域住民との連携を強化し、地域住民だけでなく、「応援したい」という想いがある全ての人々が共に文化を紡ぐ場を作りたいと考えています。
これらの取り組みを通じて、「お金の不安なく夢を追える社会」と「伝統文化が次世代に継承される社会」という二つの理想を同時に実現していきたいと考えています。子どもたちの未来を切り拓くパートナーとして、これからも全力で活動を続けていきます。
IMPACT(あなたの行っている活動は社会にどのような影響を与えているか)
「子どもたちの可能性は無限大だ」—私たちの金融教育プログラムを経験した若者たちは、自分の人生を自らの手で切り拓く自信と知識を獲得しています。国際コンテストでの入賞、メディア露出を通じた社会的認知拡大により、「お金の教育」という新たな視点が日本社会に浸透し始めています。一人の不登校児だった私の経験は、同じ境遇にある子どもたちに「未来は変えられる」という希望のメッセージとなり、教育と経済の架け橋として、次世代を担う若者たちの力になっています。
金融教育プログラムは、国際コンテストでの受賞歴や実践的な参加実績により、金融市場を実体験する実践型教育として高い成果を上げています。国際的にはペンシルベニア大学ウォートン校の投資コンペやフィンランドのJ-StarXプログラムでの高評価、さらに松下政経塾スピーチコンテストでの優良賞受賞により、活動の実効性と社会的評価を獲得するまでに至りました。
この活動を通じて見えてきた最も大きな成果は、子どもたちの目の輝きが変わることです。「お金のことなんて自分には関係ない」と思っていた若者たちが、実践的な体験を通じて「自分の未来は自分で創れる」という確信を持ち始めます。プログラム修了6ヶ月後の追跡調査では、参加者の42%が実際に少額からの資産運用を開始し、その93%が長期的な資産形成の視点で継続しているという結果が得られました。
また、不登校という逆境を乗り越えた個人の成長ストーリーは、同様に困難を抱える学生への勇気と具体的な学びの提供として、大きなインパクトを生んでいます。この取り組みは大手証券会社のYouTube番組、高校生プレゼン大会 イェール大学成田助教授講評枠選抜LIVEなどのメディアでも取り上げられ、起業家オーディション番組への出演を通じて私個人の活動を多くの人から評価いただくきっかけになりました。現在もInstagramやその他SNS、対面での経営者の方への講習登壇という形で継続的な情報発信と合わせて、若年層への金融教育の裾野を広げることに貢献しています。