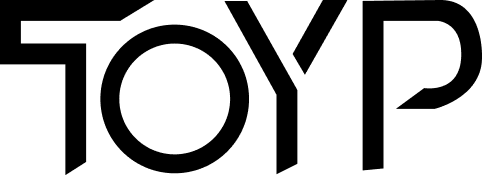| 氏名 | 悉知信 |
| 所属企業・団体名 | 茨城のいじめ問題を考える会 |
| 所属企業・団体役職 | 代表 |
| 推薦青年会議所 | |
| 活動カテゴリー | 青少年育成、世界平和、人権 |
| SNS・HP | X(旧Twitter)アカウント:https://x.com/akkun7373 Instagramアカウント:https://www.instagram.com/akkun7373/ 公式HP:https://sites.google.com/view/akirashicchi/ |
活動エリア及び活動内容
私は茨城県水戸市を拠点に、全国の自治体や国の行政機関と連携しながら、いじめや不登校問題の解決に向けた活動を展開しています。具体的には、いじめ被害者や保護者が安心して悩みを共有できる交流会(座談会)の定期開催をはじめ、これまでに150名以上の政治家・専門家・自治体関係者・弁護士・NPO団体と対談し、提言活動を行ってきました。また、文部科学省やこども家庭庁との意見交換を重ね、水戸市議会には「いじめ防止条例の制定を求める陳情」を提出するなど、制度改革にも取り組んでいます。さらに、日本弁護士連合会のシンポジウムへの登壇や、新聞・テレビ・ラジオなど合計40回以上のメディア出演を通じて、いじめや不登校問題の社会的認識を高めることにも尽力しています。これらの活動を通じて、「いじめや不登校は個人の問題ではなく、社会全体で改善すべき課題である」という意識の醸成に貢献できたと考えています。
活動内容写真




経歴 自己PR
私は、小6の時に最後は骨折に至るほどのいじめ被害を経験し、その後2年間不登校となるなど、学校での理不尽な環境に苦しんだ過去があります。しかし、その経験を「同じように悩む子どもたちの力になりたい」「もう将来の子ども達に同じ思いをさせたくない」という強い想いに変え、社会に働きかける活動を始めました。現在は「茨城のいじめ問題を考える会」の代表として、被害者支援や政策提言活動を精力的に行い、水戸市議会への陳情提出、文部科学省やこども家庭庁との意見交換など、行政や法律の力を活用したアプローチに取り組んでいます。また、高校1年生で行政書士試験に合格し、法律の専門知識を活かした支援の可能性も模索しています。メディア発信にも力を入れ、ネットニュースや新聞各社の取材を受けることで、いじめ問題の社会的認知を高める活動も展開しています。
私が目指すのは、過去の自分のようにいじめや不登校に苦しむ子どもたちが生まれない社会です。そのために、被害者支援の拡充、教育現場の制度改革、法律の整備を通じて、子どもたちが安心して生活できる環境を作ることを目標としています。高校生であったとしても、当事者が政治に対して社会に対して声を上げることで、具体的な変化を生み出せることを証明し、社会全体の意識を変えていくためにこれからも活動を続けていきます。
VISION(この活動を通してどのような未来を実現したいか)
私は、過去の自分のようにいじめ被害や不登校に苦しむ子どもたちが生まれない社会を実現したいと思っています。もちろんそれを実現する前段階として、子供たちが一人で悩むことなく、適切な支援をすぐに受けられる社会を実現したいと考えています。現状では、多くの被害者が声を上げることができず、学校の対応が不十分なまま心身に深刻な影響を受けるケースが後を絶ちません。私は、行政・法律・教育・心理の各分野が連携し、被害者が迅速かつ適切な支援を受けられる仕組みを構築することで、子どもたちが安心して学び生きていける環境を整えたいと考えています。また、学校現場におけるいじめ対応の強化と、加害生徒・児童への教育的な指導の充実を推進することで、いじめの発生自体を減らし、仮にいじめ事案が発生しても被害者が泣き寝入りしなくても良い状態を構築し、問題の根本的な問題解決を目指します。
ACTION(ビジョンを実現するために今行っている具体的な活動)
私の活動の中心は、政治家や専門家、自治体、弁護士などとの意見交換・提言活動です。意見交換を重ねながら、国会議員や自治体の議員に具体的な提言を行い、制度改革を目指しています。これまでに、文部科学省副大臣や国連子どもの権利委員、国会議員、水戸市議の9割を含む150名以上の方々と意見交換を行い、いじめ問題や不登校支援の必要性について訴えてきました。しかし、提言だけで法律や制度を変えるのは容易ではありません。だからこそ、対談や意見交換の様子をSNSで発信し、社会全体の認識を変えることにも力を入れています。そうした発信を通じて、海外メディアからも取材の依頼を受けるようになり、メディアの力も活用しながら、いじめ問題に取り組んでいます。
また、いじめ被害者や経験者向けの座談会(交流会)を月に1回開催しています。活動を進める中で、被害者や経験者が安心して気持ちを話せる場がほとんどないことに気づき、そのような場を作りたいという思いから、県議会議員や社会福祉協議会と交渉し、協力を得ながら実現しました。交流会には政治家や行政関係者にもオブザーバーとして参加していただき、被害者の生の声を政策立案の参考にしてもらっています。さらに、新聞などの地元メディアの取材を積極的に受けることで、いじめや不登校の実態を広く社会に伝えています。参加者からは「このような場でないと安心して気持ちを話せないので、とてもありがたい」といった声をいただいており、リピート参加される方も増えています。本来、このような交流会が必要ない社会を目指すべきですが、支援を求める人がいる限り、ライフワークとして続けていきたいと考えています。
さらに、水戸市議会に対して「いじめの防止に関する条例の制定を求める陳情」を提出しました。活動を進める中で、水戸市にはいじめ防止条例が存在しないことを知り、その必要性を強く感じたことがきっかけです。条例があるだけですべての問題が解決するわけではありません。しかし、市として「いじめを許さない」という姿勢を示し、市や教育委員会、学校などの関係者の責任の所在を明確にすることには大きな意義があります。現在、この陳情は市議会の委員会で審議が進められており、議員の方々からは「結果がどうなろうと一石を投じた意義は大きい」「本来は我々がやるべきことなのに申し訳ない」といった声も寄せられました。
いじめ問題は、大人のハラスメント問題と同様に、人間の本質に関わる部分があり、一朝一夕での解決が難しい課題です。だからこそ、まずは社会の意識を変えることが重要だと考えています。そのために何ができるのかを日々考え、提言活動やSNSでの発信、被害者支援、条例制定の推進など、多方面からのアプローチを続けています。
IMPACT(あなたの行っている活動は社会にどのような影響を与えているか)
私の活動は、社会に大きな影響を与えています。まず、地方自治体や国の行政機関が、いじめ問題への対応を強化する動きにつながっています。実際に、私の陳情を受けて水戸市議会ではいじめ防止条例の審議が進められ、他市町村の先進事例が共有されるなど、具体的な政策の変化を生み出しています。また、県議会議員との意見交換を経て、いじめや不登校支援の課題が実際に議会で取り上げられるなど、政策レベルでの影響が広がっています。
さらに、いじめ被害者向けの交流会(座談会)を実施することで、多くの被害者や保護者が孤独を感じることなく、適切な支援へとつながる機会を得られるようになっています。加えて、メディアを通じた発信により、いじめの実態や被害者が泣き寝入りせざるを得ない現状が広く知られるようになり、社会全体の意識変革にも貢献しています。こうした活動を通じて、被害者が声を上げ、支援を受けながら前を向ける環境が少しずつ整いつつあります。
もちろん、この問題がすぐに解決するわけではなく、制度改革や社会の意識改革には時間がかかります。だからこそ、あらゆる角度からアプローチを行い、まずは社会全体の認識を変えることを目指しています。今後も、より多くの人が適切な支援を受けられる仕組みを構築し、いじめ問題の本質的な解決に向けた意識改革を推進していきます。