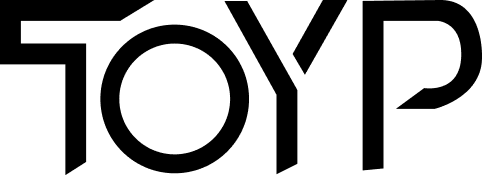| 氏名 | 立木 桃子 |
| 所属企業・団体名 | 公文国際学園高等部 |
| 所属企業・団体役職 | |
| 推薦青年会議所 | 一般社団法人横浜青年会議所 |
| 活動カテゴリー | ビジネス、経済、起業, 学術, 文化, 科学技術, 自己啓発 |
| SNS・HP |
活動エリア及び活動内容
私の研究は、「音楽を用いて、テクノロジー時代における人間の“感じる力”を支える環境を設計すること」に焦点を当てています。具体的には、感情や人格が最適化された人工的環境(AIやVRによって構成されるパーソナライズド空間)において、感情が現実から乖離していく危険性を予測し、そうした未来に対する“ストッパー”としての音楽の可能性を探究しています。
その中心には、「テクノロジーが感情を模倣・誘導する時代において、いかに人が自分自身の感情を“自分のもの”として感じ続けられるか?」という問いがあります。私はこの問いに対して、音楽がもつ曖昧さ・揺らぎ・内省を促す力に着目しています。
現在は、音楽による情動変化を脳科学的・感性工学的に捉えるためのリサーチデザインを構想中で、脳波(特にrACC領域)、心拍、呼吸などの生体データと主観的感情評価を組み合わせた実験モデルを設計しています。また、VR空間における音楽体験において「本当に感情が動く空間とは何か?」というテーマにも関心を持ち、感情反応と空間デザインの関係を可視化するための実験計画も立案中です。
さらに、AIがリアルタイムで個人の情動状態を捉え、それに応じて音楽を調整するプロトタイプの設計図も制作しており、大学進学後にはこれを実装・検証し、将来的には教育・医療・ウェルビーイング領域での応用を目指しています。
このように私は、音楽×脳科学×AI×VRという複合的な視点から、テクノロジーと共存しながら人間の感情や“内なる実感”を守り育てるための感情支援環境の探究を続けています。
活動内容写真


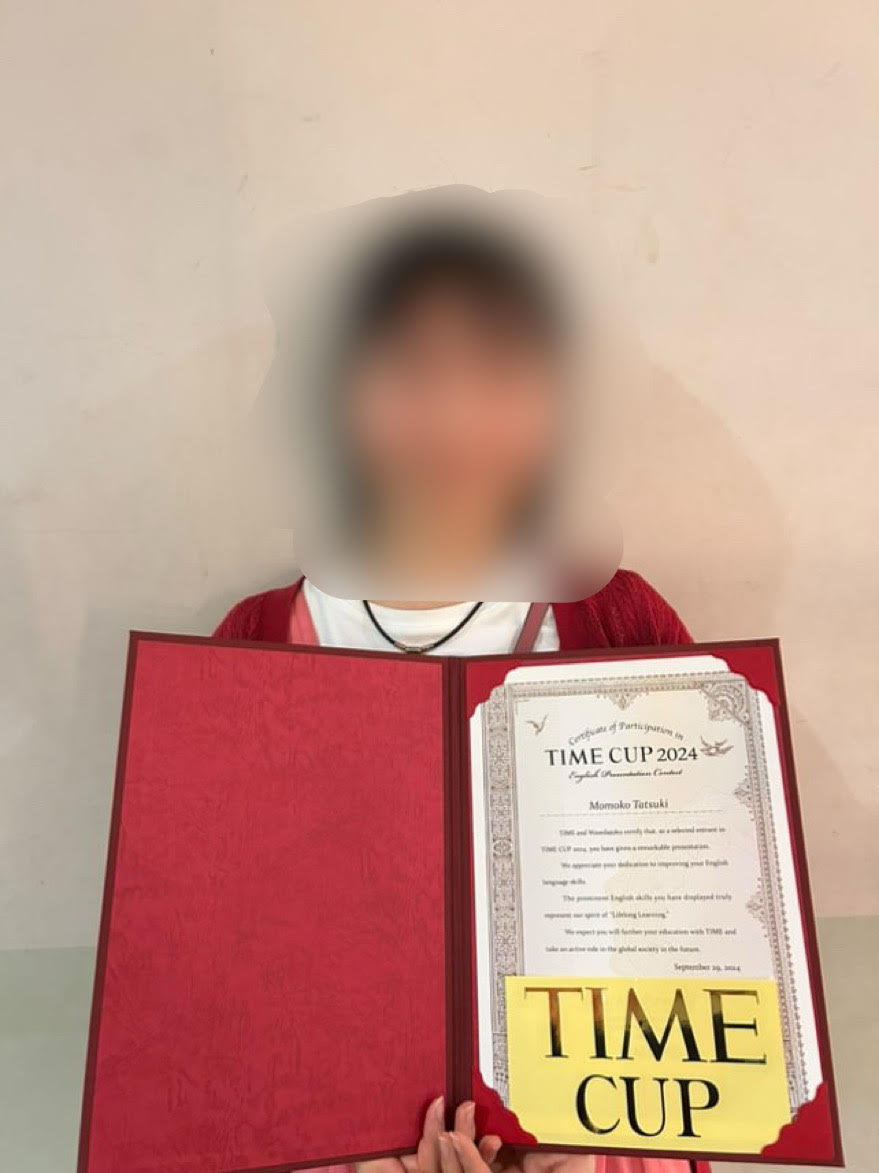
経歴 自己PR
私は、音楽を軸に脳科学・AI・VRといった学際領域にまたがる探究を行ってきました。
文部科学省「トビタテ!留学JAPAN」高校生コースの奨学生としてドイツに探究留学し、マンハイム音楽大学の講義に参加。音楽の歴史や感情との関係、ヨーロッパにおける芸術教育の在り方を体感しました。また、ニュージーランドでは名門合唱団に所属し、現地の音楽文化や言語・表現・共同体の関係についての実践的理解を深めました。
国内外の探究活動に加えて、スタンフォード大学の短期プログラムにも参加。AIモデリング、感情を起点としたVR空間設計、感情の演出と実体験の差異に関するディスカッションなどを通じて、テクノロジーと人間の内面との新しい関係性について視野を広げました。
国際的な対話活動としては、模擬国連 Inter 2024 に参加し、国際的な社会課題の構造と対話による解決のあり方について実践的に学びました。また、タイ北部での難民・少数民族支援のフィールドワークにも参加し、現地での教育・経済支援を行いました。この経験は、テクノロジーだけでは支えきれない「人間性」と「つながり」の意味を問い直す大きな契機となりました。
加えて、私はケイパビリティ(潜在能力)という概念に基づき、学生の内面と未来に向き合う対話型イベントを主催する学生団体を立ち上げました。若者が自己の感情と出会い直し、“生き方を選ぶ力”を養うための場づくりを行っています。
現在は、VR内の音楽市場の基盤作りに向けた起業も準備中です。感情の可視化とリアルタイムフィードバックを実現するAI音楽生成プロトタイプや、VR空間における音響設計の検証などの研究をしつつ、研究からの社会実装を進めています。
VISION(この活動を通してどのような未来を実現したいか)
私は、テクノロジーが進化し、無意識的欲求までが演算される時代において、感情や人格、記憶が現実から乖離していく未来を危惧しています。AIやVRが私たちの“心地よさ”を先回りして設計し、限りなく最適化された環境が提供される社会では、人が自分の感情を「自分のもの」として感じ続けることが難しくなるかもしれません。感情は演出され、選択肢は誘導され、内側の揺らぎや違和感さえも排除されていく──そんな世界に、私は大きな違和感を覚えます。
だからこそ私は、テクノロジーと共存しながらも、人間が“内的実感”を取り戻し、自分の感情と主体的につながるための文化や環境を構築したいと考えています。その鍵になるのが「音楽」です。音楽は数値化や効率化に収まりきらない、曖昧さと揺らぎを内包したメディアであり、私自身も音楽に救われ、自分自身の内面と向き合う時間を得てきました。
将来的には、音楽×脳科学×AIによる感情支援システムの社会実装を通して、教育・医療・メンタルケアの分野で、誰もが“感じる力”を失わずにいられる社会を実現したいと考えています。また、デジタルウェルビーイングや情動的デザインといった視点を取り入れながら、快適さや効率性だけでは測れない“生きている手応え”を支える技術や文化の基盤づくりに貢献したいです。
私のVisionは、感情が最適化され、管理される社会に対して、「感じる自由」と「気づきの余白」が守られる未来を提示することです。そしてその出発点として、音楽という感性メディアが、テクノロジーと人間性の間に新しい対話をもたらすと信じています。
ACTION(ビジョンを実現するために今行っている具体的な活動)
私は、「AIやVRが無意識的欲求までも最適化する時代、人は自分の感情を“自分のもの”として感じ続けられるのか?」という問いを軸に、音楽を用いた感情支援環境の設計に取り組んでいます。これは未来の人間性そのものに関わる切実な問いです。
映画『マトリックス』のように、人間が仮想空間に完全に没入し、現実と虚構の区別が曖昧になる社会が訪れる可能性は、もはやフィクションではありません。AIが先回りして理想的な“快適な空間”を設計する世界で、人は「それが本当に自分の感情なのか」を問い直すことができるでしょうか。
この問いに対して、私は音楽という曖昧で、演出しきれないメディアにこそ鍵があると考えています。音楽は、効率性やロジックでは説明できない“内的実感”を呼び起こす力を持っており、私はその力を科学と技術の視点から解明し、社会に実装しようとしています。
現在、音楽が人間の情動にどのように作用するかを検証するために、rACCを含む脳波・心拍・呼吸といった生体データと主観的感情評価を組み合わせた実験デザインを構築中です。また、感情フィードバックに応じて音楽を変化させるAIシステムの設計や、音響・空間・身体の相互作用をVR上で試作するなど、複数の視点から実践的にアプローチを進めています。
さらに、これらの研究成果をもとに、教育・医療・福祉・ウェルビーイング領域での応用を見据えたプロトタイプ設計と起業準備も進行中です。音楽が人の感情を単に癒すだけでなく、自分自身との再接続を支える“環境設計の起点”となるようなサービスや仕組みをつくりたいと考えています。
並行して、「感情と言葉と生き方」をめぐる対話の文化を根づかせるべく、学生団体でのケイパビリティ支援活動や対話イベントも継続しています。これはテクノロジーだけではカバーしきれない“感情の文化的基盤”を支えるもう一つの実践です。
私は、テクノロジーの進化に人間の感情が飲み込まれてしまう未来ではなく、「感じること」「揺らぐこと」が尊重される未来の設計に、音楽を通して一石を投じていきたいと考えています。
IMPACT(あなたの行っている活動は社会にどのような影響を与えているか)
私の活動は、AIやVRが感情を演出・最適化する未来に対して、「人が自分の感情を自分のものとして感じ続けられるのか?」という問いを社会に投げかける行為そのものです。効率や快適さばかりが重視される時代に、“曖昧さ”や“揺らぎ”を受け止める感情環境の再設計を試みることは、テクノロジーの進化と人間の感性との関係性を問い直す挑戦でもあります。
この活動は、特に若年層の孤独や情動の自己理解の困難さといった現代的課題に対して、新たな支援の視点を提示しています。実際に、学生団体による対話イベントでは「自分の気持ちを初めて言葉にできた」「わからなさを大切にしていいと思えた」などの声が多く寄せられており、内的実感の回復と“自分自身との再会”を促す場として機能しています。
また、感情×音楽×テクノロジーという学際領域におけるプロトタイプ構築や社会実装の試みは、教育・医療・ウェルビーイング分野にも応用可能な基盤づくりとなっています。これらの研究が進むことで、感情の可視化・共有・支援が新たなかたちで実現され、感情が単なる“データ”や“商品”ではなく、「人間性の核」として尊重される社会を後押しする力になりうると考えています。
私の活動は、「感情が最適化されすぎた社会」で失われがちな“内側からの気づき”を取り戻す文化の再構築を目指しています。そしてその文化的インフラを、音楽という感性メディアを通して支えたいという思いが、すべての根底にあります。