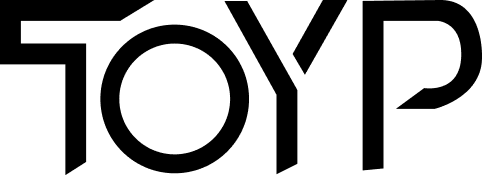| 氏名 | 森 萌彩 |
| 所属企業・団体名 | 滋賀県立虎姫高等学校新聞部 |
| 所属企業・団体役職 | 滋賀県立虎姫高等学校新聞部部長 |
| 推薦青年会議所 | 一般社団法人長浜青年会議所 |
| 活動カテゴリー | ビジネス、経済、起業, 文化, 倫理・環境, ボランティア |
| SNS・HP | 滋賀県立虎姫高等学校HP http://www.torahime-h.shiga-ec.ed.jp/ |
活動エリア及び活動内容
学校のある滋賀県長浜市を中心に活動しています。学校内のニュースの他、地域の歴史や環境、地域を盛り上げている人や企業などを幅広く取材し、発信しています。さらに新聞製作だけにとどまらず、取材を進める中で見つけた地域の課題解決に向けて、自分たちでできることを考え、近年は小谷城址の保全や米川の環境保全活動など地域の人と協働して地域を盛り上げる活動にチャレンジしています。
活動内容写真
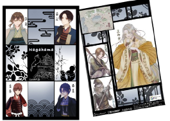



経歴 自己PR
①文化部のインターハイといわれる「全国高等学校総合文化祭」新聞部門で6年連続最優秀賞を受賞しています。②「2023 SDGsQUESTみらい甲子園関西大会」でファイナリスト、また2024同甲子園で「BLUEVプロジェクト賞」を受賞しました。③「2024高校生ボランティア・アワード」全国大会に出場しました。④「第28回ボランティア・スピリット・アワード」(全国)でコミュニティ賞を受賞しました。
VISION(この活動を通してどのような未来を実現したいか)
自分たちの住むまちが、「若者がこのまちに住み続けたい」と思えるまちになることを目指して活動をしています。若者が地域の魅力を発見・発信し、持続可能な形で地域を盛り上げる未来です。長浜市は2022年にゼロカーボンシティ宣言をしました。地球規模の環境保全にも目を向け、また一方で滋賀・長浜の魅力ある歴史、豊かな自然を大切にして、それらを活かした魅力あるまちづくりをしたいと考えています。
ACTION(ビジョンを実現するために今行っている具体的な活動)
具体的な活動として大きく 2 つを挙げます。
1つ目は長浜市の脱炭素化に向けた取り組みを取材する中で知った、お米からできたプラスチックと、自分たちが地元の歴史を知ってもらうために作った長浜出身の武将のイラストをコラボして、長浜の観光や歴史遺産の保全に役立てようと「武将クリアファイル」を作ったことです。きっかけは私たちの学校のある長浜市で 2022 年の 3 月に 2050 年に二酸化炭素排出をゼロにする、「ゼロカーボンシティ宣言」が出されたことでした。今、高校生の私たちは2050年に40代…脱炭素のために何ができるのか…考えました。そんなとき新聞部の取材で「お米から作るプラスチック」であるバイオマスプラスチック「ライスレジン」を知りました。お米を使ったプラスチックであるライスレジン使えば焼却時の二酸化炭素は約 30%削減できます。これなら長浜市の「ゼロカーボンシティ宣言」にも貢献できます。取材では田植えから稲刈りまで参加しました。一方、新聞部では、小谷城や姉川の戦い、賤ケ岳の戦いなど長浜市の歴史を紹介する「ふるさとの歴史を知る」シリーズを展開していました。紙面では生徒に読んでもらうために、長浜市ゆかりの武将のイラストを部員が描いていました。そこで考えたのがライスレジンで作る「武将クリアファイル」 です。「長浜のお米」という地域資源を使って、「長浜の武将」を地元の高校生がアピールする製品になっています。クリアファイルは小谷城戦国歴史資料館で販売されているほか、小谷城や長浜市内での行われる「ふるさと祭り」で部員たちが販売しています。土日に行われる祭りですが、部員たちも楽しみながらやっています。イラストは小谷城主の浅井長政、石田三成、七本槍で有名な片桐且元や脇坂安治などの長浜出身の武将のほか、姉川の戦いで名を馳せた磯野員昌や遠藤直経など、歴史好きの心をくすぐるマイナーな武将もそろえたラインナップで好評を得ました。クリアファイルの収益は小谷城址の保全に使用されます。クリアファイル販売のほかにも、小谷城の保全のための募金をしてくださった方の配布する虎姫
高校新聞の「ふるさとの歴史を知る」シリーズをまとめた冊子を作り、募金活動にも活用しています。
2つ目は、長浜市の中心を流れる米川で「川の喫茶店」を開き、米川の環境保全と米川を使った観光プランを考えたことです。8月の米川祭りで地域の方と協働して川の中の喫茶店
をオープンしました。多くの人が川の中に入り、歩くことで、川床がやわらかくなり、魚にとって住みやすい、産卵しやすい環境になったのは、私たちにも驚きでした。川歩きの結果、魚の餌となる新しい藻が生え、アユが戻ってきたことが確認されています。アユは琵琶湖では近年漁獲量が減少しており、生態系を守る視点からも有効な活動だと考えています。また、米川祭り当日は喫茶店だけでなく子どもたち向けにトチノミの工作講座を開き、長浜の山間部の豊かな森林資源を感じてもらえるようにしました。長浜の北部には日本有数のトチノキの巨木林があります。また、近くの中学校が琵琶湖にヨシを植える活動を長年行っています。その活動を取材し、琵琶湖におけるヨシの有用性を考える取り組みも行いました。米川祭りの前には地域の方と川の清掃を一緒に行ったり、11 月には米川でビワマスが産卵しやすくするために川床を柔らかくする作業も行ったりしました。ビワマスは琵琶湖の固有種で、漁獲量の減少が危惧されています。このように、滋賀県で最大の面積を誇る長浜市の山、川、琵琶湖までを俯瞰し、生物多様性の観点からも長浜の魅力を伝えられるような取り組みを行いました。そしてこのような活動を学校の遠足や修学旅行で実施し、環境教育にも生かせるプランに広げていけないかと、現在考えています。以上のような活動を通して地域の魅力の創出と発信に努めています。
IMPACT(あなたの行っている活動は社会にどのような影響を与えているか)
若者が地域課題に関心を持って主体的に活動をし、新聞によって広く発信することを通じて、若者たちに「自分も地域のために何かしたい」という意識を生み出し、また若者自身の可能性の発見にも繋げています。さらに地域の歴史遺産や環境保全の活動に高校生が熱心に取り組む様子は、地域の活性化につながると同時に、幅広い世代の方に共感をしていただき、地域の将来に対する期待や安心感をもたらしていると考えています。生徒自身の意識の変化もありました。活動に関わった私たち部員の感想を紹介します。「小谷城戦国歴史資料
館など、地元の方は高校生がこのような活動をすることをすごく喜んでくださり、応援してくださった。そのおかげでクリアファイルもつることができた。活動している中で地元の良さを伝えようとしている人が多いことを実感した。ただ、そのような方も高齢の方が多かったので、若者がまちづくりに参加することが大事だと気づいた」「今回の米川まつりは地元の人との協働作業でした。地元の方はとても熱くて、長浜に対する愛着を感じました。私たちも一緒に、長浜の自然を守り、魅力あるまちにしていきたいと思いました」「川歩きを通して、米川の生物の豊かさを実感しました。普段、川などの自然は日常に溶け込んでいて意識を向けることは少ないけれど、実際に米川に入ることで初めてそこで生活を営む生き物たちの存在に気づかされました。また、川歩きは生物多様性だけでなく、それを取り巻く人々の活動や、水系一体についても意識を向ける機会にもなると思いました」等、これらの活動を通して、まちづくりに関わろうとする意識が醸成されたと思います。