
今こそ新時代の旗手となれ
~地域間連携が生み出す共助社会~
【はじめに】
首都圏(栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、神奈川県の1都7県)には、日本の総人口の約35%にあたる約4430万人が生活しており、国内において大きな影響力をもっています。そして、多くの若者が多種多様な個性を育みながら、各々の未来を見つめ活力あふれる日々を送っています。その一方、国民の4人に1人が後期高齢者という超高齢化社会、いわゆる2025年問題が発生し、企業や地域を支えるコミュニティなど、あらゆるシーンにおいて人財が不足し現状を維持することが困難になると想定されます。
関東地区協議会は、各委員会事業を通じて、人財減少に起因する地域や組織の課題を地域間連携と意識変革を用いて解決し、モデルケースを広く発信します。これにより、未だかつて経験したことのない超高齢化社会が巻き起こす人財不足に対応できる「地域の枠を超えた共助社会」が構築されます。
首都圏の生産年齢人口は高齢化とともに減少し、サービスを支えてきた団体や企業は解散または廃業を余儀なくされています。国立社会保障・人口問題研究所の資料によると、このまま2040年を迎えた場合、社会保障や地域経済など様々なものが崩壊すると想定されています。関東地区協議会ではこの危機的な状況を打破するために、関東地区内155LOMと連携を図り、類似した団体や企業のマッチング、事業承継のサポートについて地域間連携を活かし実施します。「個」で解決するという意識を変革し、地域を跨ぐ連携から持続可能な経済発展のための成功事例をつくり広く発信します。
諸外国に比べて日本企業のダイバーシティ化は著しく遅れており、このままでは事業やサービスに必要な人財が不足し、存続が困難になると想定されます。この状況を打破するためにも、協働相手としてダイバーシティ化の参考になる首都圏の企業をピックアップし、155LOMのメンバーや地域企業に対し、人財雇用の多様化はもちろんのこと、従業者の働き方そのものにも様々な価値観を柔軟に取り入れるよう運動を展開して参ります。地域企業がこのようなこれまでにない取り組みを行うには負担も当然に発生すると考えられますが、地域を代表する経営者が多く集う関東地区協議会が率先して提唱することで意識が変革され、企業が存続できるモデルケースが首都圏に浸透します。
2023年に行われたIMD(国際経営開発研究所)の調査によると、日本は65歳以上の割合が主要64か国の中で最も高く、国際競争力は年々低下しており、成長率は64か国の中でほぼ最下位に位置しています。このような状況を踏まえ、関東地区協議会では関東地区内155LOMのメンバーに対し、青年会議所がもつ国際の機会を通じて国際対応力の強化を図るとともに、IoTを活用するためのデジタルリテラシーの向上を念頭に置き、ヒトの高付加価値化を促します。また、地域企業に対しては、インバウンドに対応するために地域間で協同し、モノやサービスの高付加価値化を推進します。人や企業が国際を意識した新たな視野をもって成長することで、世界における日本の競争力が向上します。
高齢者の増加は避難行動要支援者の増加に直結し、災害発生時における被害が増大します。関東地区協議会では、ブロック協議会との連携を図りながら関東地区内に住む多くの人々へ共助の取り組みの必要性について発信するとともに、この取り組みに民間企業や個人も含めた全ての人々が連携し、協働しながら全世代の人々の防災意識を底上げします。また、首都圏に拠点を置くLOMメンバーの事業所と他団体との協力体制の締結を推進するとともに、155LOM、8ブロックが連携し、災害発生時の被害を最小限に抑えていきます。
さらに、高齢化社会の影響は青年会議所にも及びます。2022年に行われた総務省統計局の調査によると、国内の成人の80%が40歳以上となる中、入会資格を満たす人口が減少していることなどにも起因し、多くのLOMがメンバー数の減少による影響を受け、人財不足によりLOMの活動が制限されてしまっていることは大きな課題です。関東地区協議会ではブロック協議会と連携し、LOM単体では構築が難しい運動を関東地区協議会が主体となり、複数のLOM同士の共創で推進するとともに、動員を募りたい事業や広域に向けて発信したい事業の広報活動を支援し、社会から見た青年会議所に対する関心を高めます。また、硫黄島渡島事業を本年度も開催し、出向者には青年会議所ならではの機会を提供することで個人の成長につなげます。そうすることで、LOM単体で難しいとされる事業展開や機会の提供を関東地区協議会がサポートし、155LOMの活動の幅を広げます。
第73回関東地区大会桐生大会は、関東地区協議会最大の運動発信の場として各委員会の集大成を参加者に発信します。開催地の桐生市、みどり市の歴史や特徴に触れ、参加者に地域の魅力を体感していただくとともに、関東地区協議会ならではのスケールメリットを活かした手法を通じて、主管LOMの地域での知名度を向上させます。さらに、人財不足問題に対する具体的な対策イメージを155LOMにもち帰っていただき、各々の活動エリアでの活用を推奨します。
このように超高齢化社会では、生産年齢人口を含めあらゆる人財が不足すると想定されますが、地域間連携と意識変革によって多くの問題が解決できます。関東地区協議会はそのモデルケースを広く発信するとともに社会に浸透させることで、前例のない人財不足を解消する「地域の枠を超えた共助社会」を構築します。
【持続可能な経済発展のための地域間連携】
2022年に行われた厚生労働省の人口調査によると、首都圏の高齢化率は全国平均や地方圏に比べて低くなっているものの、団塊Jr世代が高齢者になる2040年には高齢者の割合が全人口の35%を超えることが予測されています。一方で首都圏の生産年齢人口の割合は年々減少傾向にあり、2025年には首都圏全人口の約60%、2040年には53%まで減少すると予測されています。そのため、2025年は戦後の日本を築き上げてきた団塊世代の後期高齢化、2040年に控えている団塊Jr世代の高齢化、年々減少していく生産年齢人口といった社会課題と向き合わなくてはいけない年になります。過疎化が進む地域にとって、これらの社会課題は地域経済に深刻な影響を与えており、近年では特に「後継者不足・従業者不足」により黒字であっても廃業を余儀なくされる企業が増加しています。こうした廃業が続くと雇用喪失につながり、地域経済が縮小するとともに地域に不可欠なサービスやインフラが衰退し、地域の持続可能な経済発展が困難になります。
そこで、後継者不足や従業者不足に悩む地域団体や企業を首都圏から広く募り、同じ課題をもつ異なる地域の団体や企業をつなぎ、首都圏全体で各地域に必要なサービスを維持するための地域間マッチングを推進します。また、会社組織においては6000名のメンバーが在籍する関東地区協議会の強みを活かし、M&Aも視野に入れた事業承継のサポートを行い、既存の事業を後世に残す取り組みを推奨して参ります。そして、これらの取り組みを通じて得た成果が首都圏に浸透するように、青年会議所のネットワークを活用し広く発信します。
地域経済の衰退は地域そのものの衰退を意味しています。しかし、個では難しいと感じていたことも、意識を変革し、これまでに無かった選択肢を模索すれば新たな活路が見出されます。関東地区協議会では、各地域の連携を活かした運動を各地会員会議所とともに推進し、情報共有を通じてお互いを助け合う持続可能な経済発展のためのモデルをつくります。
【企業の新時代に向けたダイバーシティ化】
過去の実績を信用し組織の伝統を大切にするという我慢や根性が重要視されてきた近代は、産業革命や資本主義の発展、科学技術の進歩など、現代を築き上げるためには欠かせない時代でした。そして近年は知性やコミュニケーション、情報やネットワーク、イノベーションなど、目に見えないものが価値を生み出し、個人を大切にする時代が始まりました。この時代において注目されているのは多様性/ダイバーシティです。日本でも経済産業省が発行した「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」をはじめとして、企業のダイバーシティ化が推進されています。超高齢化社会の影響により生産年齢人口の減少に歯止めがかからなくなる今だからこそ、地域企業はしっかりとこの状況を認識する必要があります。
諸外国では、企業のダイバーシティ化は既に20年以上も前から注目されている一方で、日本は、IMDの調査によると2019年時点で主要63か国中でも最下位に位置するなど、企業の順応性が低いことも起因し、ダイバーシティ化の浸透は諸外国に比べて遅れをとっている状況です。このまま企業のもつ概念が変革されなければ、事業やサービスに必要な人財が不足し存続が困難になると想定されます。
関東地区協議会では首都圏の企業に対し、外国人や65歳以上のシニア層、障がい者など、これまで力を入れてこなかった人財の雇用に向き合う機会を提供し、雇用の多様化を推進していきます。さらに、育児や介護と両立させながら働かなければならない、ライフステージが変わっても働き続けたい、自分の好きな時間や場所で働きたい、複数の仕事をしたいなど、働く個人のライフスタイルや価値観の多様化に適応した、ダブルワークやビジネスケアラーなどといった働き方の多様化を推進します。これらの事業を同じ首都圏内で雇用や働き方の多様化によって著しく業績を伸ばした企業と協同して行い、成功事例を広く浸透させる取り組みを行います。
社会課題と企業の現状の間には大きなギャップが存在しています。この状況をしっかりと認識し時代の変化に対応できる企業を育てることは、人財が不足する高齢化社会にとって非常に大切です。関東地区協議会は、ダイバーシティ化など多様な選択肢を取り入れた企業が増えるように運動を展開します。
【世界に対応するための高付加価値化】
2023年に行われたIMDの調査によると、日本の65歳以上の人口比率は主要64か国中で最も高く、高齢化による労働人口減少という他国が経験したことのない問題が私たちの地域や企業に影響を及ぼし始めています。このような状況だからこそ、他国から競争力を向上させるための様々な情報を得る必要がありますが、日本人は海外への関心が低いというデータもあります。これからの時代を担う私たちは、海外から学ぶ意識を積極的にもち、広い視野で自国と向き合わなければなりません。
実際に、日本の経済は停滞を続けています。日本はGDP(国内総生産)世界4位の経済大国ではありますが、IMDによる世界競争力ランキングでは64か国中35位と過去最低値となっています。また、実質GDP成長率は62位となっており、こちらも見逃せない現状です。
関東地区協議会では「ヒト」の高付加価値化を実現するために、関東地区内155LOMに在籍するメンバーに対して、JCI Asia Pacific Area Conference(アジア太平洋開発会議)やJCI World Congress(世界会議)などJCI諸会議への参加を通じ国際的な視野の醸成を図るとともに、開催地の歴史や文化の中からこれまでにない価値観を学びます。そして、IoTを活用し国内に拠点を置く中でも海外へとマーケットを広げられるよう、メンバー以外の方々も対象としたデジタルリテラシーの向上を図る事業を行います。また、「ヒト」に対してだけではなく「モノ」や「サービス」における付加価値の向上も重視し、各地域の企業に対し価格競争ではなく高付加価値化を意識した上で地域間連携を活かしたインバウンド戦略を推奨して参ります。
このように、国際の機会に触れることや国際的な観点を視野に入れながら、人財においても地域企業においても高付加価値化を実現させます。2025年問題を転機と捉え、関東地区内155LOMのメンバーや地域企業の価値が向上し成長することができれば、人口が目減りする中でも日本は世界における国際競争力を向上させることができます。
【ALL関東での防災・災害対応】
1923年9月1日に10万人以上の方が被災した関東大震災から100年以上が経過しました。近年でも、北陸地区における令和6年能登半島地震、九州地区における平成28年熊本地震、東日本大震災など全国各地で大地震は頻発しています。首都圏においてもM(マグニチュード)7クラスの地震が30年以内に約70%の確率で発生すると予想されており、明日にでも100年ぶりの悪夢が私たちの身に降りかかることも否定できない緊迫した状況です。
近年最も被害が甚大であった東日本大震災における死者の年齢別内訳を見ると、60代が19.1%、70代が24%、80歳以上が22.1%であり、全体の65.2%が高齢者であることがわかります。高齢化が進み避難行動要支援者が増加することは、災害発生時における被害も大きくなることを意味しています。絶命に至らぬとも避難行動要支援者の心身のケアや避難の長期化を考慮した避難生活の環境確認も含め、防災に対する備えを一層強化することが求められています。
関東地区協議会では、地域での被災者支援体制を向上するために自治体、地域住民、地域を跨ぐ企業の三者による防災協定締結を、地域への関わりが深く、異業種が在籍する青年会議所の特徴を活かして推進します。また、頭打ち傾向にある防災意識を変革するためにブロック協議会との連携を図りながら、関東地区内に住む多くの人々に自助、公助だけでなく幅広いかたちでの共助の取り組みの必要性を学ぶ機会を提供するとともに、若い世代を含めた全世代の防災意識の底上げを行います。さらに、昨年より施行を開始した災害支援ツール(リスクロ)の維持管理や各LOMを巻き込んだ防災訓練を実施し、防災マニュアルのアップデートを図るなど関東地区協議会としての既存の仕組みをより盤石なものにします。
喉元過ぎれば熱さを忘れるとのことわざに象徴されるように、大災害が起こった直後には防災に対する意識が高まるものの時間の経過とともにその意識が薄れる傾向が見られます。関東地区協議会は、凡事徹底を念頭にこれらの施策を行うことで有事においての被害を最小限に抑えます。
【ブロック連携によるLOM支援】
日本青年会議所関東地区協議会会則には、本協議会は本会の定款で定める目的達成のため、当該地区内ブロック協議会の意見を総合調整し、青年会議所運動の進展に寄与することを目的とする。と記載されています。LOM支援の観点においても、関東地区協議会はLOMが抱える課題解決のためにブロック協議会と連携を図っていくことが重要です。
高齢化社会の影響は青年会議所にも及び、40歳以上の成人の割合が全体の80%以上を占める中、2024年期首時点で、関東地区協議会155LOMのうち約60%となる91LOMがメンバー数30名以下となっています。さらに、JC運動に対しての向き合い方がわからないメンバーが増えている現状があります。このように人財不足によりLOMの活動が制限されてしまっていることは、関東地区にとって大きな課題と言えます。
そこで、関東地区内のメンバー不足に悩むLOMの中でも、特に超高齢化社会に伴う人財不足を課題とする複数のLOMをターゲットとし、ブロック協議会と連携を図りながらマッチングを行うとともに、関東地区協議会がリードして事業を共創します。さらに、各ブロック内で大きな動員を募りたい事業や広域に向けて発信したい事業を、関東地区協議会が中心となり、多彩なコンテンツを活用して年間を通じて多方面に発信、共有していきます。この取り組みによりLOMで構築された事業がより効果を増すとともに、事業を構築したLOMが広く認知され関心が高まります。また、関東地区協議会が長年にわたり行っている硫黄島渡島事業は、日本の歴史に直接触れ先人への感謝の念や日本人としての誇りを学ぶことができる事業です。このような他では経験できない事業に参加する機会を提供することで、時代を担う自覚と責任感を醸成します。
私たちは志を同じくし相集い、同じ時代に青年会議所に熱い情熱を注いでいます。入会したLOMによって得られる出会いや体験に格差が生じることのないよう、関東地区協議会はブロック協議会との連携によるLOM支援とスケールメリットを活かした事業を通じて、155LOMの活動の幅を広げて参ります。
【モデルケースをつくり上げる関東地区大会】
第73回関東地区大会桐生大会では、関東地区協議会最大の運動発信の場として各委員会の「2025年問題に起因する人財不足」に対する取り組みを結集し、開催地である桐生市、みどり市の課題解決を通じて、首都圏全域のモデルケースとなることを目指します。
桐生市は群馬県の東部に位置し、かつては繊維産業で栄えましたが、その産業依存の結果、地域の未来に対する危機感に世代格差が生じています。さらに、人口は毎年約1500人が減少し、出生率は1を切り、高齢化率は37%を超えています。特に地元就職率がわずか3%という現状は、若者の流出を引き起こし、社会減を招いています。また、繊維産業の遺産である建造物の老朽化も問題となっておりその改修が進んでいません。本大会では、各委員会の取り組みを最大限活用した開催地の課題に対する具体的な解決策を当日ご参加いただく地域の方々や155LOMの皆様に発信します。これにより、関東地区協議会の存在感をより一層実感し、会に対する興味関心が高まるとともに、ご参加いただいた方々には各地域で抱える課題を解決するためのヒントをもち帰っていただきます。他にも、開催地の繊維産業の遺産である歴史的建造物や自然豊かな環境、歴史的まち並みに触れていただくことで、開催地の魅力を体感する機会を提供します。
関東地区協議会は、主管LOMである一般社団法人桐生青年会議所並びに群馬ブロック協議会と関東地区協議会のスケールメリットを活かした大会構築を通じ、主管LOMのブランド力を活動エリア内で向上させるとともに、メンバーのモチベーション向上を図ります。このように、関東地区協議会と主管LOM、地域の様々なパートナー、そして関東地区内155LOMとの連携を通じて本大会を構築することで、各々が高齢化社会のもたらす人財不足問題に対するモデルケースを認識し、首都圏各地の課題解決につなげていきます。
関東地区大会は70年以上の長きにわたり歴史を刻み、それぞれの時代において主管LOMをはじめとする多くのLOMや、開催地をはじめとする広い社会、そして参加者に様々な「益」をもたらし、本年まで紡がれてきました。その歴史がこれからも連綿と受け継がれていくように、関東地区内155LOM、在籍する6000名のメンバー、首都圏に住む4430万人にとって最大限価値のある大会を構築します。
【おわりに】
私は埼玉県の川越市にサラリーマン家系の次男として生を受け、地元の中学校を卒業したのち、16歳で解体工事現場の日雇い労働者として生計を立て、18歳で命を落としかけたことをきっかけに人生の岐路に立ち、19歳で現在の事業所を起業、22歳で事業所を法人化すると同時に青年会議所に入会しました。
青年会議所には「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友情」3つの信条が存在しますが、私はこの中で特に「個人の修練」に重きを置き15年間にわたり活動を行って参りました。「社会への奉仕」や「世界との友情」は昨今、他団体やSNSを含むあらゆるコミュニティにおいても体感することができますが、「個人の修練」を体感できる機会を見つけ出すことは非常に難儀です。そのバッチとネームプレートをつけている間は、事業所の規模や一般社会においての肩書は関係なく、誰もが白帯で自己の成長に向き合います。間違いなくこの青年会議所という道場は若者を大きく成長させる力をもっています。なぜなら、人より秀でるものを何ももたず入会した私が、今こうして6000名のメンバーの皆様に対し自身の意見を綴る機会をいただいています。これが何よりも根拠となるのではないでしょうか。
幼少の頃より大人のいうことを聞く子が良い子で、聞かない子が悪い子、テストの点が高い子が優秀で、低い子が問題児と定義づけられて育った私たち日本人は、大人になってからも同じ評価方法によって選定されることが多く見受けられます。社長や上司の指令に実直に従う社員が良い社員で、そうでない社員が悪い社員、難易度の高い資格や学歴を保有している人財が優秀で、そうでない人財が平凡と定義されるシーンが頻繁に存在します。結果として私たちは過去より導き出された「正解」に向かう取り組みが得意な反面、未だ経験したことのない物事や、今存在していない価値観を生み出すという創作の意欲において大きな怠りを感じます。
超高齢化社会という未だかつて経験したことのない局面が私たちの国に訪れました。昨日までの「通常」は常に塗り替えられ、対応に追われる日々が首都圏を襲います。今こそ、私たちは修練の日々の中で、昨日までの「正解」を疑い、「成長」に向けて歩み始めなければなりません。
私はこの境地に際し、出会うべくして出会った仲間たちとの絆を胸に、これまでの修練の日々の集大成を発揮すべく全力でこの職務を全うすることをお誓い申し上げます。
さあ今こそ、ともに「新時代の旗手」となりましょう!
【基本理念】
今こそ新時代の旗手となれ
〜地域間連携が生み出す共助社会〜
【基本方針】
1. 地域間連携による持続可能な経済発展の仕組み構築
2. 地域間連携による多様な価値観を取り入れた企業存続モデルの創造
3. 高付加価値化による国際競争力の向上
4. 地域間連携をいかした防災・災害対応の確立
5. ブロック間連携をいかした LOM 支援方法の確立
6. 関東地区大会の実施による運動の発信
7. 適正な財政と資金調達による強固な財務体制の構築
8. 規律遵守による組織運営の安定化

委員長 福本 浩一
(所属:一般社団法人横浜青年会議所)

委員長 吉野 隆雅
(所属:一般社団法人桐生青年会議所)

委員長 安藤 博昭
(所属:公益社団法人東京青年会議所)

委員長 吉田 篤
(所属:一般社団法人茨城南青年会議所)

委員長 田所 大和
(所属:一般社団法人下館青年会議所)

委員長 小川 雄大
(所属:公益社団法人立川青年会議所)

委員長 鴨狩 真義
(所属:公益社団法人野田青年会議所)
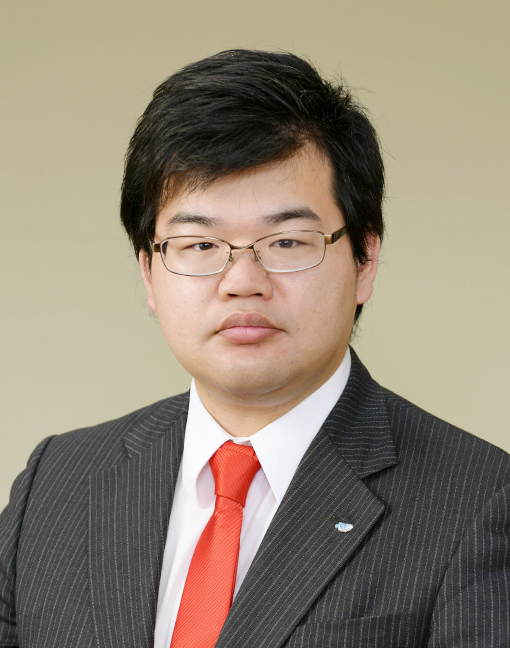
局長 中島 啓亨
(所属:公益社団法人川越青年会議所)
[138] (一社)足利青年会議所
[149] (一社)栃木青年会議所
[313] (一社)佐野青年会議所
[349] (一社)鹿沼青年会議所
[356] (一社)宇都宮青年会議所
[425] (一社)真岡青年会議所
[427] (一社)小山青年会議所
[535] (一社)那須野ヶ原青年会議所
[550] (一社)たかはらさくら青年会議所
[558] (一社)黒磯那須青年会議所
[785] (一社)日光青年会議所
[050] (公社)水戸青年会議所
[141] (一社)土浦青年会議所
[306] (一社)笠間青年会議所
[340] (一社)日立青年会議所
[409] (一社)高萩青年会議所
[457] (一社)北茨城青年会議所
[495] (一社)常陸太田青年会議所
[523] (一社)竜ヶ崎青年会議所
[588] (一社)石岡青年会議所
[607] (一社)茨城南青年会議所
[654] (一社)下館青年会議所
[656] (一社)下妻青年会議所
[658] (一社)古河青年会議所
[673] (一社)結城青年会議所
[684] (一社)常総青年会議所
[688] (一社)潮来青年会議所
[706] (一社)境青年会議所
[708] (一社)つくば青年会議所
[720] (一社)坂東青年会議所
[744] (一社)牛久青年会議所
[759](一社)鉾田青年会議所
[763] (一社)ひたちなか青年会議所
[771] (一社)かしま青年会議所
[003] (公社)前橋青年会議所
[033] (公社)高崎青年会議所
[108] (一社)桐生青年会議所
[257] (公社)伊勢崎青年会議所
[258] (公社)館林青年会議所
[267] (一社)富岡青年会議所
[295] (公社)太田青年会議所
[357] (一社)藤岡青年会議所
[372] (一社)渋川青年会議所
[509] (一社)沼田青年会議所
[538] (公社)安中青年会議所
[676] (一社)おおらか青年会議所
[140] (一社)熊谷青年会議所
[215] (公社)川越青年会議所
[230] (公社)行田青年会議所
[238] (一社)秩父青年会議所
[266] (公社)所沢青年会議所
[284] (一社)深谷青年会議所
[290] (公社)川口青年会議所
[309] (公社)春日部青年会議所
[395] (公社)草加青年会議所
[415] (公社)こだま青年会議所
[524] (一社)朝霞青年会議所
[542] (一社)桶川青年会議所
[548] (公社)飯能青年会議所
[564] (一社)越谷青年会議所
[575] (一社)加須青年会議所
[596] (一社)鴻巣北本青年会議所
[619] (一社)入間青年会議所
[640] (一社)八潮青年会議所
[644] (一社)久喜青年会議所
[648] 吉川青年会議所
[657] (一社)三郷青年会議所
[674] (一社)羽生青年会議所
[686] (一社)狭山青年会議所
[693] (公社)比企青年会議所
[699] (公社)西入間青年会議所
[718] (一社)東入間青年会議所
[728] (一社)幸手青年会議所
[766] (公社)埼玉中央青年会議所
[772] (一社)とだわらび青年会議所
[159] (一社)茂原青年会議所
[195] (公社)千葉青年会議所
[285] (一社)銚子青年会議所
[311] (一社)かずさ青年会議所
[322] (一社)勝浦いすみ青年会議所
[334] (一社)市川青年会議所
[359] (一社)旭青年会議所
[381] (公社)松戸青年会議所
[401] (一社)佐原青年会議所
[414] (一社)八日市場青年会議所
[428] (一社)館山青年会議所
[456] (公社)船橋青年会議所
[459] (一社)東金青年会議所
[467] (公社)柏青年会議所
[488] (一社)八千代青年会議所
[500] (一社)成田青年会議所
[539] (公社)野田青年会議所
[553] (公社)習志野青年会議所
[604] (公社)佐倉青年会議所
[614] (一社)鎌ヶ谷青年会議所
[621] (一社)市原青年会議所
[690] (公社)浦安青年会議所
[704] (一社)流山青年会議所
[732] (一社)我孫子青年会議所
[001] (公社)東京青年会議所
[300] (公社)立川青年会議所
[330] (一社)八王子青年会議所
[370] (一社)青梅青年会議所
[373] (一社)町田青年会議所
[430] 三鷹青年会議所
[440] (一社)むさし府中青年会議所
[444] (公社)調布青年会議所
[505] (一社)国分寺青年会議所
[510] (一社)武蔵野青年会議所
[526] (一社)日野青年会議所
[543] 東村山青年会議所
[557] 小金井青年会議所
[566] 多摩青年会議所
[597] 稲城青年会議所
[645] 福生青年会議所
[675] 狛江青年会議所
[680] 清瀬青年会議所
[725] (一社)小平青年会議所
[736] 昭島青年会議所
[747] 東大和青年会議所
[767] あきる野青年会議所
[774] 西東京青年会議所
[776] 東久留米青年会議所
[013] (一社)甲府青年会議所
[190] (公社)富士五湖青年会議所
[374] (一社)都留青年会議所
[462] (一社)韮崎北杜青年会議所
[463] (一社)大月青年会議所
[551] (一社)山梨青年会議所
[565] (一社)甲州青年会議所
[618] (一社)南アルプス青年会議所
[665] (一社)笛吹青年会議所
[711] (一社)峡南青年会議所
[746] 上野原青年会議所
[014] (一社)横浜青年会議所
[022] (一社)川崎青年会議所
[030] (公社)横須賀青年会議所
[139] (公社)小田原青年会議所
[164] (公社)平塚青年会議所
[231] (公社)三浦青年会議所
[233] (公社)秦野青年会議所
[264] (一社)逗子葉山青年会議所
[305] (公社)鎌倉青年会議所
[316] (公社)相模原青年会議所
[335] (一社)藤沢青年会議所
[404] (公社)茅ヶ崎青年会議所
[417] (公社)厚木青年会議所
[563] (一社)寒川青年会議所
[646] 伊勢原青年会議所
[652] (一社)大和青年会議所
[660] (一社)座間青年会議所
[667] (一社)綾瀬青年会議所
[682] (公社)海老名青年会議所
[703] (公社)津久井青年会議所
[729] (一社)あしがら青年会議所

委員長 福本 浩一
(所属:一般社団法人横浜青年会議所)

委員長 吉野 隆雅
(所属:一般社団法人桐生青年会議所)

委員長 安藤 博昭
(所属:公益社団法人東京青年会議所)

委員長 吉田 篤
(所属:一般社団法人茨城南青年会議所)

委員長 田所 大和
(所属:一般社団法人下館青年会議所)

委員長 小川 雄大
(所属:公益社団法人立川青年会議所)

委員長 鴨狩 真義
(所属:公益社団法人野田青年会議所)
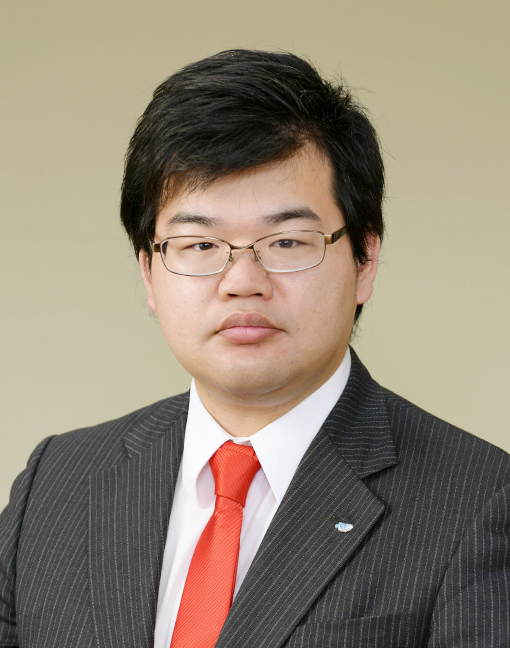
局長 中島 啓亨
(所属:公益社団法人川越青年会議所)
〒350-0065
埼玉県川越市仲町1-12
TEL : 049-229-1810/ FAX : 049-225-2101