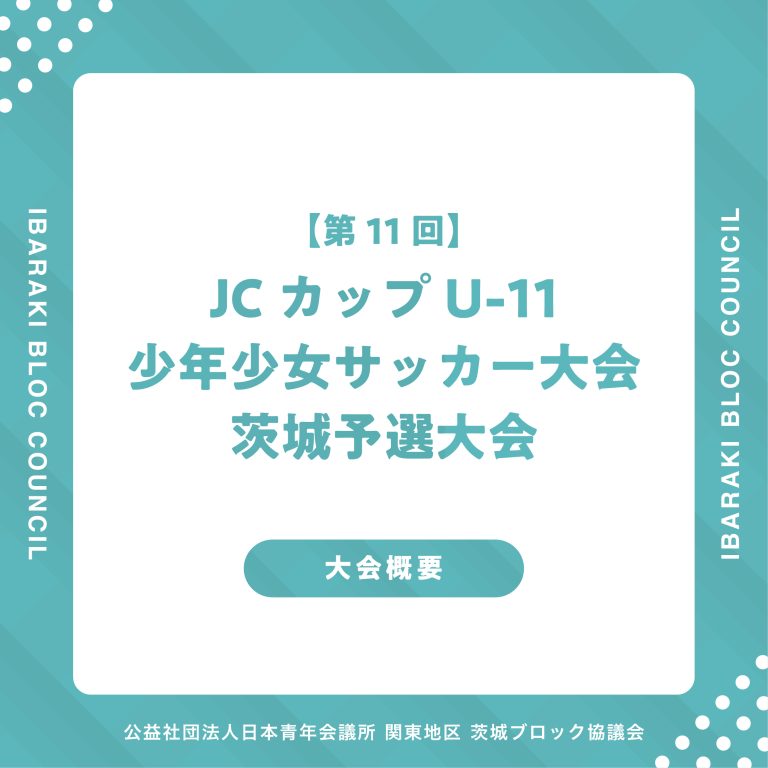【はじめに】
JCには、個人の価値観を変える出会いがあり、その出会いには飛躍的な成長を与える力があります。JCに入るまでの私は、地域の未来を本気で変えようと奮闘している同世代がこんなに多くいるとは思っていませんでした。日々の仕事をこなすことしか考えていなかった私にとって、熱い思いを持って運動に取り組む先輩や仲間の姿は、まぶしく映ってはいましたが、当初はどこか遠い存在であり、私とは違う世界に属していると斜に構えていました。しかし、日々のJC活動の中で、人との出会いを重ねていくうちに、確かな変化を私の中で感じるようになりました。入会の翌年に、副委員長として茨城ブロック協議会に初めて出向しました。それまでLOMで理事を経験したこともなければ、議案に触れたこともなく、全てが未知の経験でした。ようやく作り上げた議案に対して、諸会議で厳しい意見をいただくこともありましたが、気迫だけは負けてたまるかという気持ちで議案と深夜まで向き合いました。議案が可決した後は、事業の参加者を集めるため、茨城県内をくまなく奔走して関係各所に足を運びました。事業の閉会まで不安しかありませんでしたが、事業を無事に終えた時の安堵感と満足感は、これまでの人生で感じたことがないものでした。しかし、私が一番強く感じたことは、多くの仲間に支えられたからこそ、事業を成し遂げることができたということでした。委員長がいたからこそ、議案を作ることも、厳しい意見に向き合うことも、茨城県内を朝から晩まで駆けずり回って参加者を集めることもできました。委員会のメンバーがいたからこそ、当日の円滑な運営や参加者を始めとする関係者への細やかなケアまですることができました。私は出向によって、価値観を変える出会いを経験し、仲間との交わりの中で成長を実感することができました。しかし、このような価値観を変える出会いは特別なものではなく、JCでは誰もが体験することができます。茨城には、地域の未来を変革しようと日々奮闘する約700名の同志がいます。40歳までの同じ年代でありながら、職業も、経歴も、信条も、性格も異にする人々が、約1年という時間の中で、出会い、交わり、時に衝突しながらも、同じ目的に向かって運動を起こしています。その中で、リーダーシップの開発と成長を促され、そして、翌年また違う人々と交わっていきます。JC特有の流動性の高い組織文化が、個人に偶然の出会いによる化学反応をもたらし、加速度的な成長を促しています。私は、この稀有な組織文化を押し進め、茨城県内のメンバーが互いに資質を高め人格を陶冶し合うことにより、個人の成長と組織の発展の好循環を実現する茨城ブロック協議会を目指します。
【茨城ブロック協議会として行うLOM支援のあり方】
茨城県内23LOMの総合連絡調整機関である茨城ブロック協議会の運動は、LOMなくしては成り立ちません。各地のLOMは、JCI MISSIONに謳われているように「青年が社会により良い変化をもたらすためにリーダーシップの開発と成長の機会を提供する」ことを使命とし、地域の未来をより良く変えていくべく地域に根差した運動を展開しています。
茨城ブロック協議会としては、LOMが地域に運動を展開し続けていくための支援が必要です。現在どのLOMでも、会員数の減少傾向に加え、アカデミー会員の割合の増加、卒業までの在籍年数の短期化により、LOMとしての精神性や知識の継承が困難になっているという共通の課題を抱えています。一方で、茨城県内には、会員数が100名を超えるLOMもあれば、人数が一桁台のLOMもあるなど会員数の分布には差があり、拠点とする範囲も、4つの特色あるエリアにわかれています。当然、LOMごとに固有の課題もあります。そのため、各LOMに共通する課題と、特定のLOMに存在する課題とを振り分けて、効果的な支援を行っていかなければなりません。情報を一方的に提供して終わることや単に事業を丸投げして負担感だけを与えてしまうことがないように各LOMの現状を把握した上で、茨城ブロック協議会の持つ人的、物的資源をLOMの発展に活用します。茨城ブロック協議会が各LOMのパートナーとなり、各LOMメンバー並みの情熱をかけて、各LOMの運動の最大化を図らなければなりません。
各LOMへの効果的な支援をするため、次の三つの項目で取り組みを行います。一つ目は、地域に潜む課題に果敢に取り組む人財の定着、二つ目は、課題への挑戦を強める自律的な組織の形成、三つ目は、社会開発に取り組む事業の展開です。第一の人財の定着という点については、アカデミーメンバーの育成とLOM運営の中核を担う人財の育成が課題となります。第二の自律的な組織の形成という点については、組織の基盤となる会員の拡大、効率的かつ効果的な会議の運営などの組織力の強化が課題となります。第三の社会開発事業の展開については、茨城県という地域が抱える問題を解決するための運動をいかに構築していくかが課題です。単独での事業開催が困難なLOMについては、茨城ブロック協議会が共同で事業を構築する形で支援を行います。第三の点では特に、JCのブランディング、地域の人的及び物的基盤の強化、伝統の上に新たな歴史を紡ぐブロック大会の構築に取り組んでいきます。これら三つの項目が結びつくことで、個人に加速度的な成長を促し、LOMの運動の最大化を後押しすることになります。以下では、これら三つの項目を軸として、茨城ブロック協議会の行動を示していきます。
【地域の課題に果敢に取り組む人財の定着】
茨城県では、現在約700名のメンバーがJC運動に携わっていますが、そのうち4割以上がアカデミー会員となっています。そして、LOM単位で見るとおよそ3分の1のLOMで、アカデミー会員が半数を超えています。加えて、卒業までの在籍年数が低下している現状があります。アカデミー会員が多いということは、組織として流動的であり、多様な価値観を持った人財が硬直化した組織文化に新風を起こすという正の側面が期待できる反面、卒業をするまでの在籍年数が短いため、JCの運動を十分に理解し、展開することなくJCを去ってしまい、組織として培ってきたJCの精神性や知識が継承されることなく、目的意識の低下に繋がります。なにより、JCに在籍していたにも拘わらず「リーダーシップの開発と成長の機会」が十分に提供されなかったことによる負の側面も見過ごせません。そのため、アカデミー育成事業は、次の二つの観点から、効果の最大化を考えなければなりません。一つ目は、アカデミー会員がJAYCEEとして成長するきっかけとなることです。アカデミー会員の中には、JC運動に対する理解がまだ十分でないメンバーもいると考えられますし、事業構築にすでに取り組んでいるものの、JC運動の目的がわからず、どのようなアプローチをすれば良いかわからないというメンバーもいると考えます。JCには、明確な使命と目的があり、掲げた理想を実現するためのアプローチも確立されています。アカデミー育成事業に参加することにより、JAYCEEとしての目的意識が芽生え、当事者意識を持って運動に参画できる機会とします。そして、二つ目は、茨城県内で志を同じくするメンバーと出会い終生の友情を育むきっかけとなることです。同年代と交流をすることは、JCで活動をしていく上で、LOM単位の垣根を越えた視野を広げる機会となり、苦楽を共にすることで得られる経験は何物にも代えがたい財産になります。
また、LOMが地域で運動を展開していくためには、アカデミーの育成に加えて、LOM運営の中核を担うメンバーの育成も欠かせません。青年会議所は、主に、理事長、副理事長、委員長などの役職者による縦の繋がりを重視する階層的構造の組織形態を取っており、上位の役職者が下位の役職者を指導していくことで、下位の役職者が実践的な訓練を積み、その中でJCの理念を理解し、順番に上の役職に昇っていく仕組みが取られています。しかし、アカデミー会員が多くの割合を占めていること、卒業までの在籍年数が低下していることにより、JCの理念が十分浸透していないうちに、責任ある立場として事業を構築し、下位の役職者への指導に当たらなければならない事態に陥っています。LOM運営の中核を担うメンバーの一人ひとりが、地域の課題を的確に捉え、最大限の効果を生む事業の構築とメンバーの成長に向けて指導ができる人財になることで、LOM全体の発展を促します。
【地域の課題への挑戦を強める自律的な組織の形成】
茨城ブロック協議会では、2022年から2026年までの中間ビジョンを2021年に策定しており、その中で、「各地会員会議所が目指す会員拡大人数年度ごとの100%達成を補助し、2026年ブロック協議会人数1000人となっている状態をつくる」という目標を掲げています。会員拡大に成功しているLOMはあるものの、全体としては会員数減少傾向に歯止めがかかっていません。会員拡大に関しては、まずは全LOMを対象に会員拡大に対する体制の底上げを図ることが必要です。JCには、設立当初から現在に至るまで長年にわたり蓄積されてきた会員拡大手法があります。しかし、アカデミー会員が増えている中では、LOMで拡大手法の継承がうまくいかず、目的意識が育たないうちに拡大の取り組みを始めざるを得ず、初動が遅れてしまい、十分な成果が出ることなく1年が終わってしまうことが懸念されます。そのため、早いうちから拡大に取り組むことにより、伝播させたいJCとしての理念を理解してもらった上で、拡大手法や成功事例を共有して、各LOMが切磋琢磨しながら拡大に邁進できる体制を構築していきます。また、特に人数が少なく拡大活動を実施すること自体が難しいLOMに対しては、拡大活動に入り込んで実践の中で拡大に対する動機付けを強固なものとし、自力で拡大活動ができるよう支援をしていきます。
また、JCは、メンバーから預かった会費を効率的かつ効果的に使って地域課題の解決に向けた事業構築をするために、民主的な会議で議論を行う自律的な組織となっています。このような自律的な組織を維持するためには、組織の中で個々が責任を自覚し、役割を全うすることが必要です。そして、役割を全うすることに伴って個々の立ち振る舞いにも厳格さが求められます。これまでは、JCに長く在籍する中で多くの出会いを重ね、様々な役割を経験することで、自然と組織の中での責任を自覚し、役割を全うする意識を強めることができました。しかし、近年のように在籍年数が十分でないうちに卒業するメンバーが増えてくると、長く時間をかけて意識醸成を図ることが難しくなっていきます。そのため、在籍年数の長短に拘わらず、自律的な組織を形成し、維持するために、各LOMを対象として理事会などの会議のあり方や組織としてのプロトコルを学べる研修を実施していきます。また、出向の機会を活用し、出向メンバーが自律的な組織を学ぶ機会を作ります。自律的な組織を作ることで、個々の議案に対して、腰を据えて建設的な議論をすることが可能となり、ひいてはLOMとして、より地域の課題に対して果敢に挑戦していくことが可能となり、地域の発展に大きく寄与することに繋がります。
【広報と交流によるブランディング】
茨城ブロック協議会ではこれまで意識的に、ブランディングに取り組んできました。JCのブランディングとは、地域に対して、JCの運動を認知してもらい、他の同種団体と異なるJC独自の魅力を感じてもらい、組織としての信頼感を高めることです。そして、ブランドを維持、向上させるためには、ブランドを創造し、伝達し、保護することが必要です。そのうえで、ブランドを伝達するためにはJCの活動を対外に発信する視点が、ブランドを創造し、保護するためには、JCの価値を対内に浸透させる視点が大切です。
JCのブランドを地域に伝達させるためには、広告・宣伝活動が必須ですが、いまだにJCが何をしているかが知られていなかったり、地域にインパクトを与える事業を構築しているにも拘わらず、広告・宣伝が十分でなかったことから成果があげられなかった事例も見受けられます。近年は、SNSの活用が当たり前になり、生成AIの利用が広がり始めたことで、情報の発信が容易になったがゆえに情報にあふれています。その中でJCが地域に認知されるためには、適切な媒体を選択し、伝えるメッセージとその対象を明確に設定することが必要です。広告・宣伝を個人の質任せにすることなく、規模の大小に拘わらずLOMがJCのブランディングに継続的に取り組める環境を作らなければなりません。そのため、茨城ブロック協議会としてブランディングを意識した統一的な広告・宣伝活動と組織的な取り組みを行うとともに、各LOMで戦略的な広告・宣伝活動を担う人財を育て増やします。これにより、茨城ブロック協議会及び各LOMがJCブランドの伝達を効果的に行うことができ、ひいては地域のリーダーを育成し、地域の課題に挑戦するというJCのブランドをより強固なものとしていきます。
また、JCのブランドを創造し、保護するためには、JAYCEEとして行動することになるメンバーの一人ひとりにJCの価値が染み渡っていなければなりません。JCを通じた交流を図ることで、同じ志を持った仲間と巡り合い、JC活動に対する意識を向上させお互いを高め合うことができれば、ひいてはJCの理念を浸透させることに繋がります。茨城ブロック協議会では、これまで、全体での交流、エリアごとの交流、出向者同士の交流、性別や年齢を限定した交流など様々な交流の機会を提供してきました。未知の出会いは個人を刺激し、加速度的な成長を促し、JCの価値の浸透に繋がります。2026年度も、これまでの交流のみならず、未知の出会いを創出するためLOMの垣根を越えた交流の機会を設け、メンバーがまだ見ぬ仲間と出会える機会を作っていきます。
【地域の人的、物的基盤を強化する】
日本では、過去から一貫して国民一人ひとりが日本の政治を動かしているという認識が低く、特に若者全体に共通する現象として、選挙での投票に対する責任感が低下しているという指摘があります。地方の政治は住民の自主的な意思に基づいて行われなければならないところ、若者の主権者意識が低調であれば、政治参画が進まないばかりか、地域の発展の担い手も育たないという負の連鎖が続きます。負の連鎖は我々の手で断ち切らねばなりません。若者が地域の課題に向き合い、解決策を地域に提言し、本気で変えたのだと実感できる機会を作ることで、主権者意識を醸成していく取り組みが必要です。
茨城県では、過去約10年を見ても、多くの災害が発生しています。その中には、平成27年9月関東・東北豪雨、令和元年房総半島台風(台風第15号)、令和元年東日本台風(台風第19号)、2023年の台風第2号及び台風第13号など、多くの住家被害のみならず人的被害をもたらす災害もありました。防災・減災インフラの整備等により、災害発生が抑止・軽減された地域もありますが、ハード面のみで自然災害のすべてを防げるわけではなく、災害による被害を最小限に抑える減災の取り組みが肝要です。そして、どのような境遇の人であっても災禍を等しく減らしていくには、地域住民が自覚的に地域の減災に動かなければなりませんので、地域における減災の担い手育成を図っていきます。
茨城県では、県全体としてみれば、人口減少並びに出生数及び出生率の低下が想定を超えるペースで進み、高齢化と相俟って、労働供給制約や人手不足が進行しています。さらに、若者や女性が東京を中心とする首都圏へ移動しており、人口減少に拍車をかけています。このような中で当面は人口が減少することを受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済を成長させることを目指していく必要があります。他方で、全国的にインバウンドの増加、特に、地方特有の食や景観、自然、文化、芸術、スポーツなどを評価して地方を訪れ、産品やサービスを求める外国人は増加しています。観光需要がコロナ禍前と近い水準まで回復している茨城においても、年間を通して安定した需要を見込める観光型資源を造成し、地域の経済発展にさらに取り組んでいく必要があります。これまでも地域経済の担い手である産業、行政、高等教育機関、金融機関などが個別に取り組んで来ていますが、成果が十分には現れていません。そこで、各LOMが地域に根差した産業、行政、高等教育機関、金融機関などの関係各所をつなぐ結節点となることで、地域が主体的に課題解決へ取り組む環境を整え、茨城県全体の経済発展に貢献します。
【伝統の上に新たな歴史を紡ぐブロック大会】
茨城ブロック大会は、茨城ブロック協議会における最大の運動発信の場です。そして、主管するLOMにとっては、茨城のスケールメリットをいかした事業が展開できる舞台となります。2026年度の第55回茨城ブロック大会は、土浦市、かすみがうら市、阿見町、美浦村の4市町村を活動エリアとする一般社団法人土浦青年会議所が主管します。活動エリアの中心である土浦市は、霞ヶ浦と筑波山を臨む、水と緑に恵まれた歴史と伝統のある茨城県南部の中核都市であり、近世には、霞ヶ浦湖畔に築かれた城下町として、また、水戸街道の陸上交通、霞ヶ浦を経由した水上交通の要地として繁栄しました。近代には、常磐線が開通し、養蚕・生糸業や醬油製造などの産業振興により、県南第一の商業都市に発展しました。近年の土浦市では、20歳代前半の年齢階層につき、特に東京圏への転出が大幅に超過しているところ、若者の定着等に課題があるため、愛着を持てるまちに変えていこうと地域資源に着目した取り組みを行っています。
茨城ブロック協議会としては、土浦青年会議所と共に、伝統の上に新たな歴史を紡ぐブロック大会の実現を目指します。茨城ブロック協議会と土浦青年会議所が核となり、行政、企業、団体などと連携して、地域に住まう人々が自ら地域のために行動を起こすことを促し、世代を超えて地域に物的、精神的資産を残せる運動を展開します。他方で、メンバーにとっても、茨城というスケールメリットをいかした学びを得ることで、飛躍的な成長に繋がります。ブロック大会が地域とメンバーの成長を促し、その結果として茨城県全体の発展へと繋げます。
また、今後のブロック大会について、メンバーの数が少ない、LOMの基盤が十分整っていないなどの理由から、主管立候補を躊躇する声が寄せられています。まずは、ブロック大会の主管に手を挙げ、大会を成功させるという明確な目標を持つことにより、むしろLOMとして、開催に向けて勢いを付けることもできると考えます。そこで、主管立候補に名乗りを上げやすくするため、LOMの実情に合わせた大会規模の設定、無理のないPR活動、副主菅LOMとの連携促進など、どのようなLOMであってもブロック大会を主管できる体制整備を行います。主管LOMと一緒になって汗をかきながら、地域の市民が自立的に地域課題に取り組む好循環を生み出す大会を構築できるよう邁進していきます。
【おわりに】
JCの運動には常に成長のきっかけが用意されています。時に自分自身の限界以上を求められることもあります。限界を突破するために、自分自身と向き合い自分が無意識に作り上げている壁を乗り越えなくてはいけません。地域をより良くするためには、幾度となくもがき苦しむこともあります。しかし、志を持って地域に光を当てようと挑戦しているのはあなた一人ではありません。苦難を共にする仲間の存在とその仲間と過ごした日々があなたを飛躍的な成長に導くでしょう。
成長の一つひとつはいわば細く脆い繊維かもしれませんが、繊維が撚り合わさることで太く強い糸が創り出されます。メンバー一人ひとりが成長を実感し、成長したメンバーの輝く個性が経糸と緯糸となって織りなされることで、地域のリーダーたちが課題解決に向けて活躍する活気あふれる茨城を実現してまいります。